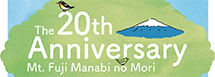モニタリング活動
植生調査 2006年度報告書
■調査方法
「まなびの森」区域内には、フォレストアーク入口の林道分岐付近から斜面上方に向かって設置した延長1170メートルの基線上に、モニタリングのための固定調査区が設置されている。(表1)
今年度は、このうち森林に設置した5ヶ所(ブナ自然林、ヒノキ人工林(若齢)、ヒノキ人工材(壮齢)、ウラジロモミ人工材、人工林風倒ギャップ)において調査をおこなった。これらの調査区では2000年から2001年にかけて、樹木の測定と草本を含む種組成の調査をおこなっており、今回はこれと同様の項目を調査することによって、過去およそ5年間での変化を明らかにした。調査区の面積は10メートル×10メートルを基本として、樹木のサイズ等に応じて100平方メートルから900平方メートルとした。
具体的な調査項目と方法は以下のとおりである。
1) |
毎木調査 |
2) |
樹冠投影図 |
3) |
植生調査 |
表1 各固定調査区の概要
調査区 |
標高(m) | 面積 (平方m) |
*林齢(年) | **密度 (本/ha) |
群落高(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| ケヤキ植栽地 | 1110 | 500 | 8(1998年植栽) | - | 2~3 |
| ブナ植栽地 | 1140 | 400 | 6(2000年植栽) | - | 1~2 |
| ブナ自然林 | 1190 | 900 | 140< | 410 | 26 |
| ヒノキ人工林(若齢) | 1090 | 100 | 24 | 2300 | 8 |
| ヒノキ人工林(壮齢) | 1180 | 200 | 46 | 1950 | 14 |
| ウラジロモミ人工林 | 1140 | 100 | 61 | 1800 | 14 |
| 人工林風倒ギャップ | 1220 | 100 | (41) | 700 | 10 |
*林齢は森林管理簿(静岡森林管理署)による
**直径10センチメートル以上の立木密度
■調査結果
1.ブナ自然林
1-1.調査区の概要
この調査区は、富士山の南側斜面を代表するブナ林の典型的な部分に設置したものである。ブナとケヤキの大径林が点在し、これらが林冠を占めている。その下層にミズキ、サワシバ、チドリノキ、エンコウカエデ、ヤマボウシなどが生育する。低木層には株立ちしたアブラチャンが多くみられる。林床にはササが生育せず、多数の草本種が生育する。スズタケが欠落する原因としては、土壌の浅い位置に火山灰が固結した不透水層があり、そのため土壌表層がつねに湿潤でスズタケの生育に適さないことが考えられる。
1-2.樹木の変化
直径階別の本数分布をみると、5-10センチメートルに本数のピークがあり、50センチメートルまでは連続的に本数が減少しながら、逆J字型の分布をしている。2001年と2006年を比較すると、分布型に大きな変化は無い。樹高階別の本数分布をみると、6-8メートルにピークがあることは変わりない。
1-3.種組成の変化
調査区内のいくつかの種では、2000年から2006年にかけて、出現頻度または優占度に大きな変化がみられた。減少したものとしては、コアカソ、サンショウ、パイケイソウ、ヤマトウバナ、キツリフネの5種があげられる。
一方、増加した種としては、アマチャヅル、ヤマミゾソバ、ミヤマハコベ、ケチヂミザサ、アシボソ、ユリワサビ、ウマノミツバの7種があげられる。また、この中にはアマチャヅル、ケチヂミザサ、アシボソのような、本来は自然林の林床には生育しない種が含まれている。調査にともなう人の立ち入りや、草地と森林を行き来するシカによって、種子が運ばれた可能性がある。
2.ヒノキ人工林
2-1.調査区の概要
この調査区は、1982年に植林された樹齢24年の若齢のヒノキ人工林である。均質な林分であるので、面積は10メートル×10メートルの100平方メートルとした。ヒノキの密度は約2300本/haである。現在まで間伐や枝打ちは行われていない。
2-2.樹木の変化
表2に調査区内に生息する全樹木の直径と樹高を示す。おおむね順調に生育しているといえる。林冠が開いている部分で成長したホオノキが直径5センチメートルを超えていたので、追加記録した。
ヒノキの胸高直径階別の本数分布(図1)を5年前を比較すると、2001年には23本中18本が10~15センチメートルの階級に属していたのに対し、2006年には15~20センチメートルのものが13本と最も多くなった。また、樹高階別の本数分布(図2)では、2001年には大半の個体が6~8メートルの間にあったのに対し、2006年には8~10メートルに本数のピークが移動し、10メートルを超えるものも現れた。
2-3.種組成の変化
出現種数は2000年の71種から34種に大きく減少した。これにはヒノキの樹冠が拡大し、林間が閉鎖して林床が暗くなったことが影響している。
表2 ヒノキ人工林(若齢)の固定調査区に生育する樹木の直径と樹高
No. |
樹種 |
胸高直径(cm) | 樹高(m) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001年 | 2006年 | 2001年 | 2006年 | |||
63 |
ヒノキ | 11.5 | 12.5 | 5.9 | 9.0 | |
64 |
ヒノキ | 11.5 | 13.5 | 7.6 | 10.5 | |
65 |
ヒノキ | 14.0 | 16.7 | 7.1 | 10.0 | |
66 |
ヒノキ | 16.0 | 19.0 | 7.6 | 10.0 | |
67 |
ヒノキ | 11.0 | 12.8 | 7.0 | 8.5 | |
68 |
ヒノキ | 6.5 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | |
69 |
ヒノキ | 13.0 | 17.0 | 6.0 | 8.5 | |
70 |
ヒノキ | 16.0 | 20.4 | 7.0 | 9.5 | |
71 |
ヒノキ | 14.5 | 18.3 | 7.6 | 10.0 | |
72 |
ヒノキ | 11.5 | 12.0 | 5.0 | 8.0 | |
73 |
ヒノキ | 13.0 | 15.6 | 7.6 | 9.5 | |
74 |
ヒノキ | 14.0 | 19.0 | 8.1 | 10.0 | |
75 |
ヒノキ | 14.0 | 17.6 | 7.3 | 9.5 | |
76 |
ヒノキ | 12.0 | 15.2 | 7.0 | 9.0 | 3.4mで折損 |
77 |
ヒノキ | 10.0 | 11.0 | 4.0 | 6.5 | 2.5mで曲がり |
78 |
ヒノキ | 12.5 | 16.4 | 6.4 | 9.0 | 3.5mで分岐 |
79 |
ヒノキ | 13.0 | 15.0 | 6.6 | 8.0 | 5.0mでツルによる折損 |
80 |
ヒノキ | 9.5 8.5 |
11.3 13.4 |
6.5 6.4 |
9.0 9.0 |
|
81 |
ヒノキ | 14.0 | 16.4 | 6.6 | 9.0 | |
82 |
ヒノキ | 16.0 | 19.8 | 6.9 | 9.0 | |
83 |
ヒノキ | 12.0 | 13.8 | 6.3 | 8.0 | |
84 |
ヒノキ | 14.0 | 18.0 | 7.7 | 9.0 | |
85 |
ヒノキ | 12.0 | 14.5 | 6.9 | 8.5 | |
282 |
ホオヒノキ | 6.5 | 8.0 | 2006年加入 | ||
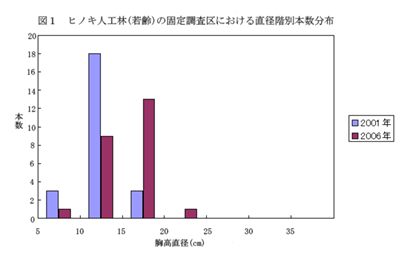
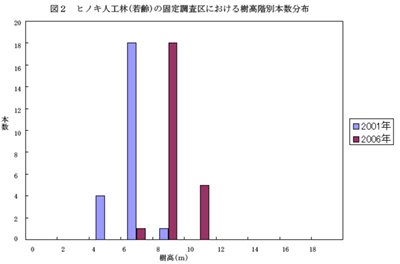
3.ヒノキ人工林(壮齢)
3-1.調査区の概要
この調査区は、1958~1959年の台風による風倒被害後、1960年に植栽された46年生のヒノキ人工林である。この林分は斜面下方で風倒跡地と接しているので、林内への風の吹き込みの影響があるかを調べるため、風倒跡地側から林内に10メートル×10メートルの方形区を2つ連ねた200平方メートルの調査区とした。過去に間伐が行われており、樹木密度が若齢林よりも低い1950本/haである。
3-2.樹木の変化
表3に調査区内に生育する全樹木の胸高直径と樹高を示す。2001年から2006年までの直径の増加は1~2センチメートル程度で、若齢林の調査区よりも少なかった。樹高はほとんど変わらないものも多かった。
ヒノキの胸高直径階別の本数分布(図3)を2001年と2006年で比較すると、2001年では15~20センチメートルのものが多かったのに対し、2006年では20~25センチメートルのものが最も多くなっていた。一方、樹高階別の本数分布(図4)では、いずれも12~14メートルに属する個体が多く、若齢林にみられたようなピークの移動は見られなかった。
3-3.種組成の変化
若齢林の調査区と比べて、ブナ自然林との共通種を多く有しており、林床の植生はブナ林とあまり変わらない。しかし、低木層が欠落するため、木本種の種数は少ない。ここでは2つの方形区とも、2001年よりも出現種数が増加した。増加した種は、いずれも林床生の草本種であった。
表3 ヒノキ人工林(壮齢)の固定調査区に生育する樹木の直径と樹高
| No. | 樹種 | 胸高直径(cm) | 樹高(m) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001年 | 2006年 | 2001年 | 2006年 | |||
| 01 | ヒノキ | 17.5 | 17.7 | 12.5 | 13.0 | |
| 02 | ヒノキ | 20.0 | 21.6 | 12.5 | 12.5 | |
| 03 | ヒノキ | 20.0 | 21.6 | 14.0 | 14.0 | |
| 04 | ヒノキ | 21.0 | 22.5 | 13.0 | 13.0 | |
| 05 | ヒノキ | 19.5 | 21.2 | 13.0 | 13.0 | |
| 06 | ヒノキ | 19.0 | 19.2 | 13.4 | 14.0 | |
| 07 | ヒノキ | 17.0 | 18.1 | 13.0 | 14.0 | |
| 08 | ヒノキ | 19.0 | 20.7 | 12.1 | 13.5 | |
| 09 | ヒノキ | 16.0 | 16.0 | 12.0 | 12.0 | |
| 10 | ヒノキ | 9.5 | 10.1 | 10.5 | 11.5 | |
| 11 | ヒノキ | 6.5 | 7.0 | 9.3 | 7.5 | 上部枯死 |
| 12 | ヒノキ | 12.0 | 12.0 | 9.9 | 10.0 | |
| 13 | ヒノキ | 21.5 | 23.6 | 13.0 | 13.5 | |
| 14 | ヒノキ | 21.5 | 22.6 | 13.0 | 13.5 | |
| 15 | ヒノキ | 14.0 | 14.5 | 11.0 | 11.0 | |
| 16 | ヒノキ | 18.5 | 19.4 | 12.2 | 12.5 | |
| 17 | ヒノキ | 18.5 | 19.0 | 12.5 | 12.5 | |
| 18 | ヒノキ | 23.0 | 24.0 | 13.5 | 13.5 | |
| 19 | ヒノキ | 9.5 | - | 1.9 | - | 枯死 |
| 20 | ヒノキ | 21.0 | 23.1 | 12.9 | 13.0 | |
| 21 | ヒノキ | 24.0 | 25.6 | 12.6 | 13.0 | 4分岐 |
| 22 | ヒノキ | 19.5 | 20.4 | 12.1 | 12.5 | |
| 23 | ヒノキ | 19.5 | 21.6 | 12.4 | 13.0 | 2mで分岐 |
| 24 | ヒノキ | 20.0 | 21.3 | 12.4 | 13.5 | 6.2mで曲がり |
| 25 | ヒノキ | 20.0 | 21.0 | 12.2 | 13.0 | |
| 26 | ヒノキ | 12.5 | 13.2 | 11.5 | 11.5 | |
| 27 | ヒノキ | 13.0 | 13.0 | 11.5 | 12.0 | 7.2mで曲がり |
| 28 | ヒノキ | 9.0 | - | 7.3 | - | 枯死 |
| 29 | ヒノキ | 11.0 | 11.0 | 10.8 | 11.0 | |
| 30 | ヒノキ | 12.5 | 12.7 | 11.5 | 12.0 | |
| 31 | ヒノキ | 26.0 | 28.0 | 13.2 | 13.5 | |
| 32 | ミツバウツギ | 5.5 | - | 6.8 | - | 枯死 |
| 33 | ヒノキ | 15.0 | 16.9 | 12.1 | 13.0 | |
| 34 | ヒノキ | 22.5 | 23.9 | 13.5 | 13.5 | |
| 35 | ヒノキ | 24.0 | 25.8 | 14.0 | 14.0 | |
| 36 | ヒノキ | 20.0 | 21.5 | 11.9 | 13.0 | |
| 37 | ヒノキ | 19.0 | 21.4 | 13.2 | 12.5 | |
| 38 | ヒノキ | 21.0 | 21.7 | 13.0 | 13.0 | |
| 39 | ヒノキ | 18.0 | 18.9 | 13.0 | 13.0 | |
| 40 | ヒノキ | 15.0 | 15.2 | 11.8 | 12.5 | |
| 41 | ヒノキ | 15.0 | 16.6 | 14.2 | 14.5 | |
| 42 | ヒノキ | 12.0 | 12.2 | 10.3 | 12.0 | |
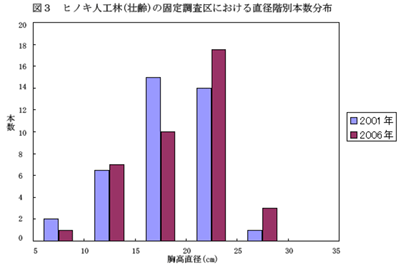
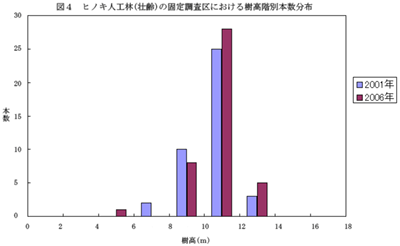
4.ウラジロモミ人工林
4-1.調査区の概要
この調査区は、1945年に植林された61年生のウラジロモミ人工林である。均質な林分であるため、面積は10メートル×10メートルの100平方メートルとした、直径20センチ前後、樹高14メートル前後のウラジロモミが、1800本/haの密度で生育している。
4-2.樹木の変化
表4に調査区内に生育する全樹木の胸高直径と樹高を示す。2001年と2006年の直径を比較すると、多くの個体では顕著な直径成長は認められなかった。樹高の増加量も少なく、先端が枯死して減少している個体もあった。
胸高直径階別の本数分布(図5)の変化をみると、2001年、2006年とも直径20~25センチメートルの個体が最も多いことは変わりなかった。樹高階別の本数分布(図6)の変化をみると、両年とも14~16メートルにピークがあったが、14メートル以下の個体が減少し、16~18メートルの個体が増加していた。
4-3.種組成の変化
2000年と比べると草本層の植被が60%から90%に増加し、出現種数も71種から90種に増加した。草本層では、イヌショウマが優占度1から3となり、増加が顕著であった。
表4 ウラジロモミ人工林の固定調査区に生育する樹木の直径と樹高
| No. | 樹種 | 胸高直径(cm) | 樹高(m) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001年 | 2006年 | 2001年 | 2006年 | |||
| 43 | ウラジロモミ | 20.5 | 21.6 | 14.1 | 14.0 | |
| 44 | ウラジロモミ | 26.0 | 28.5 | 16.2 | 15.0 | シカ剥皮 |
| 45 | ウラジロモミ | 22.0 | 22.6 | 13.6 | 14.5 | |
| 46 | ウラジロモミ | 23.5 | 25.1 | 14.2 | 15.5 | シカ剥皮 |
| 47 | ウラジロモミ | 24.0 | 25.5 | 14.4 | 15.5 | |
| 48 | ウラジロモミ | 22.5 | 25.5 | 14.6 | 14.5 | シカ剥皮 |
| 49 | ウラジロモミ | 11.0 | - | 8.0 | - | 枯死 |
| 50 | ウラジロモミ | 22.0 | 23.3 | 13.8 | 14.0 | |
| 51 | ウラジロモミ | 20.0 | 19.7 | 13.0 | 12.5 | シカ剥皮 |
| 52 | ウラジロモミ | 17.0 | 17.1 | 10.5 | 10.0 | |
| ウラジロモミ | 5.3 | - | 枯死 | |||
| 53 | ウラジロモミ | 23.5 | 24.6 | 13.9 | 13.5 | シカ剥皮 |
| 54 | ウラジロモミ | 15.5 | 16.4 | 14.2 | 13.0 | |
| 55 | ウラジロモミ | 12.0 | - | 8.3 | - | 枯死 |
| 56 | ウラジロモミ | 19.0 | 19.5 | 13.6 | 14.0 | シカ剥皮 |
| 57 | ウラジロモミ | 18.5 | 18.7 | 14.1 | 14.0 | シカ剥皮 |
| 58 | ウラジロモミ | 29.0 | 32.1 | 14.6 | 16.0 | シカ剥皮 |
| 59 | ウラジロモミ | 8.0 | - | 7.3 | - | 枯死 |
| 60 | ウラジロモミ | 22.0 | 22.5 | 12.5 | 13.5 | シカ剥皮 |
| 61 | ウラジロモミ | 13.0 | 13.4 | 10.5 | 11.5 | シカ剥皮 |
| ウラジロモミ | 7.5 | 7.7 | 11.0 | 7.5 | 先枯れ | |
| 62 | ウラジロモミ | 16.0 | 16.1 | 9.4 | 8.5 | |
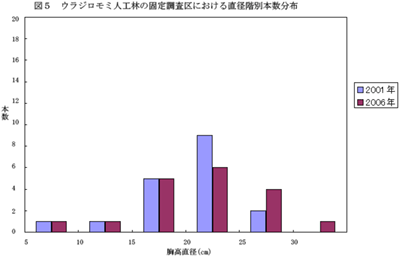
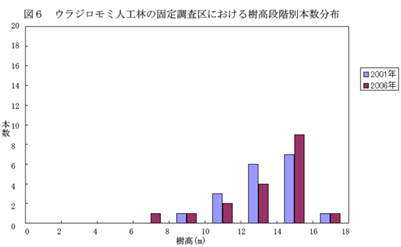
5.人工林風倒ギャップ
5-1.調査区の概要
この付近は1964年にウラジロモミ、ヒノキ、シラベが混植された人工林であるが、調査区を設置した箇所ではモミが生育していた。風倒被害が発生したときの林齢は32年で、直径20~25センチメートル程度のモミ3本が折れたために生じたギャップである。面積はギャップ全体が含まれる10メートル×10メートルの100平方メートルとした。
5-2.樹木の変化
表5に調査区内に生育する全樹木の胸高直径と樹高を示す。残存したモミの林冠木(No.176、180)の直径は、2001年から2006年の5年間に約2.5~6センチメートルも増加しており、良好な成長を示していた。No.174のイトマキイタヤは直径が5.5センチメートル、樹高が6.7メートルも増加し、著しい成長を示した。また、アブラチャンとモミ各1個体が直径5センチメートルを超え、新たに加入した。
5-3.種組成の変化
サンショウバラ、ナツグミのような林緑生の低木、ヤマブドウ、ミツバアケビ、コボタンヅル、サルナシなどのつる性木本、イケマ、ノササゲなどのつる性草本が出現することが特徴的である。2000年と比べると、出現種数は65種から80種に増加した。
表5 人工林風倒ギャップの固定調査区に生育する樹木の直径と樹高
| No. | 樹種 | 胸高直径(cm) | 樹高(m) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001年 | 2006年 | 2001年 | 2006年 | |||
| 170 | ミズナラ | 18.3 | 19.7 | 7.8 | 10.0 | |
| 171 | ナツグミ | 6.7 | 7.9 | 5.8 | 5.5 | |
| 172 | イトマキイタヤ | 5.2 | 6.2 | 6.5 | 8.0 | |
| 173 | ウラジロモミ | 16.3 | - | 4.8 | - | 枯死 |
| 174 | イトマキイタヤ | 18.0 | 23.5 | 9.7 | 16.0 | |
| 175 | モミ | 12.4 | - | 4.2 | - | 枯死 |
| 176 | モミ | 20.7 | 23.0 | 13.0 | 15.5 | |
| 177 | モミ | 16.9 | - | 6.0 | - | 枯死 |
| 178 | モミ | 23.8 | - | 5.7 | - | 枯死 |
| 179 | モミ | 22.9 | - | 6.1 | - | 枯死 |
| 180 | モミ | 24.4 | 30.7 | 11.0 | 15.0 | |
| 181 | モミ | 13.6 | 17.1 | 9.5 | 9.5 | |
| 182 | モミ | 6.2 | 8.1 | 5.8 | 7.5 | |
| 287 | アブラチャン | 5.2 | 3.6 | |||
| 288 | モミ | 5.1 | 2.3 | |||
6.植栽地の植生変化
「まなびの森」の森林再生では、単に樹木の成長をもって回復とみなすのではなく、林床の低木や草本も含めた群落としての再生を目指している。今年度は植栽地の調査はおこなっていないが、現在の植栽地の種組成がどの程度、森林に近づいているかを知るため、自然林および人工林の種組成との比較をおこなった。
湿生土壌を指標するものが多く含まれ、「まなびの森」区域の湿潤な土壌環境を反映している。人工林に転換された場所や風倒跡地でも、このような湿潤土壌を指標するブナ林構成種が多く残っていることから、群落としてまとまった種組成をもつ森林への回復が可能であると考えられる。
しかし、現在までの植栽地の種組成は、自然林や人工林とは大きく異なっている。すなわち、林床生の草本種が出現せず、かわって陽地生の低木や、草原性の種、荒地の雑草的な植物が生育している。こうちら種が減少し、森林生の種が増加していくことが、森林の再生の程度の指標となる。