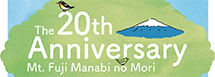モニタリング活動
植生調査 2007年度報告書
■調査方法
「まなびの森」区域内には、フォレストアーク入口の林道分岐付近から斜面上方に向かって設置した延長1170メートルの基線上に、モニタリングのための固定調査区が設置されている。(表1)
今年度は、このうち森林に設置した2ヶ所(ブナ植栽地、ケヤキ植栽地)において調査をおこなった。これらの調査区では2000年から2001年にかけて、樹木の測定と草本を含む種組成の調査をおこなっており、今回はこれと同様の項目を調査することによって、過去およそ5年間での変化を明らかにした。調査区の面積は10メートル×10メートルを基本として、樹木のサイズ等に応じて100平方メートルから900平方メートルとした。
具体的な調査項目と方法は以下のとおりである。
1) |
毎木調査 |
2) |
植生調査 |
表1 各固定調査区の概要
調査区 |
標高(m) | 面積 (平方m) | *林齢(年) | **密度 (本/ha) |
群落高(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| ケヤキ植栽地 | 1110 | 500 | 8(1998年植栽) | - | 2~3 |
| ブナ植栽地 | 1140 | 400 | 6(2000年植栽) | - | 1~2 |
| ブナ自然林 | 1190 | 900 | 140< | 410 | 26 |
| ヒノキ人工林(若齢) | 1090 | 100 | 24 | 2300 | 8 |
| ヒノキ人工林(壮齢) | 1180 | 200 | 46 | 1950 | 14 |
| ウラジロモミ人工林 | 1140 | 100 | 61 | 1800 | 14 |
| 人工林風倒ギャップ | 1220 | 100 | (41) | 700 | 10 |
*林齢は森林管理簿(静岡森林管理署)による
**直径10センチメートル以上の立木密度
■調査結果
1.ケヤキ植栽地
1999年にケヤキ等を植栽したこの調査区では、放置枝条周辺を中心に樹高5~6メートルのミズキ、キハダ、エゴノキ、クサギ等が上層を占め、低木林の相観を呈している。
●個体数の変化と空間分布
7年間の植栽木生存率は68.4%だった。職種別生存率は、ケヤキが79.3%、コナラは40%、ブナは0%、イロハモミジ100%だった。
非植栽木のうち高木性樹種では、2000年に9種44本、2003年に7種47本、2007年に10種86本に増加していた。樹種別には、ミズキが一時的に減少したものの、キハダ、エゴノキ、アオダモが顕著に増加した。これにより、2000年にミズキが52.3%を占めていたが、2007年にはミズキ27.9%、キハダ31.4%、エゴノキ16.3%、アオダモ10.5%と構成比が分散した。
低木性樹種でも、2000年に3種36本、2003年に6種52本、2007年に9種81本と、種類・個体数ともに大きく増加した。このうち多くの割合を占めていたのが、陽地にいちはやく進入する先駆的な性質が強いクサギだが、2003年までに低木性樹種全体の約8割を占めていたものの、それ以降個体数は増えていない。かわって2003年まで1本だったサンショウが、2007年には17本と急激に増加した。
枝条の集積・放置が行われている内部・周辺で、多くの樹木の生育が確認された。一方、放置枝条のない部分ではススキが密生しており、植栽木以外の新たな侵入・定着樹木はほとんどみられなかった。
表2 樹種別個体数および樹高・直径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●樹木の生長と階層構造の変化
2000年にはクサギを主とした低木性樹種が上層を占めていたが、2003年には高木性樹種が3.0~3.5mと1.5~2.5mの2箇所を占め、被圧された個体と上層を占める個体の二極化がみられた。2007年には、高木性樹種の多くが低木性樹種よりも下層にある。2.0~4.0mの階級では低木性樹種が増加した。
ケヤキは大きな苗を植栽したため、活着率は高く、2007年には多くが2.0~2.5mとヘキサチューブよりも高く成長していた。
キハダ、ミズキ、エゴノキ、ホオノキ等の高木性樹種の天然生稚幼樹は順調に成長し、ミズキで4m以上、エゴノキやホオノキは多くが3m以上に達している。
【図3】 樹高階別本数分布
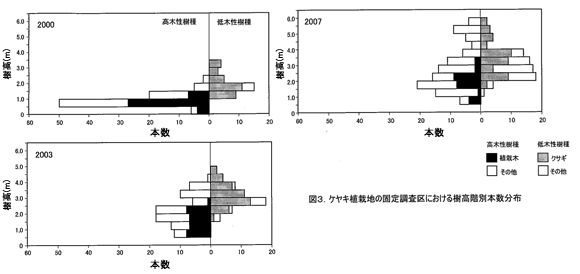
●種組成の変化
2003年から新たに22種が出現した。この中には、ブナ林に多く生育している林床生草本と好陽地性植物の両方が含まれており、一様に森林的な種組成に変化していると判断できなかった。優占度増加種の中でも、特にススキは前回より優占度が増加しており、樹木が成長していても、被圧による衰退は生じていないことがわかった。クサギは、他の樹種による被圧のため優占度が減少した。
2.ブナ植栽地
2001年に主にブナを植栽した調査区では、ケヤキ植栽地の調査区に比べ放置枝条量が少なく、緩傾斜で土壌流出が少ないため、ススキの繁茂が著しく、草原的な相観を呈している。
●個体数の変化と空間分布
6年間でブナの生存率は74.1%、マメザクラ100%だった。
非植栽木のうち高木性樹種では、2001年に12種80本、2004年に10種43本、2007年に13種107本に増加していた。樹種別には、2001年に最も多くを占めたキハダがケヤキ植栽地のミズキ同様一時的に減少したものの、エゴノキ、ヒメシャラが急増した。これにより、2001年にキハダが60.0%を占めていたが、2007年にはキハダ26.2%、エゴノキ25.2%、ヒメシャラ9.3%と構成比が分散した。
低木性樹種でも、2001年はウリノキ5本だけだったが、2004年に6種28本、2007年に7種51本と、種類・個体数ともに大きく増加した。
2007年には放置枝条に低木性樹種も出現した。放置枝条のないススキが密生した中で、高木性樹種の定着がみられた。
表3 樹種別個体数および樹高・直径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●樹木の生長と階層構造の変化
2001年には低木性樹種の個体数は少なかった。2004年には低木性樹種が上位を占めていた。2007年には高木性樹種で成長のよい個体は、低木性樹種を大きく超えていた。この調査区ではススキの繁茂が著しく、樹高2.0未満の高木性樹種はススキと競争関係にある。
ブナは小さな苗を植栽したため、2007年でも多くがヘキサチューブを抜き出ておらず、中で成長が停滞しているものもある。キハダ、エゴノキの成長は順調で個体数も増加しており、ミズキやホオノキも良好な成長である。
【図8】樹高階別本数分布
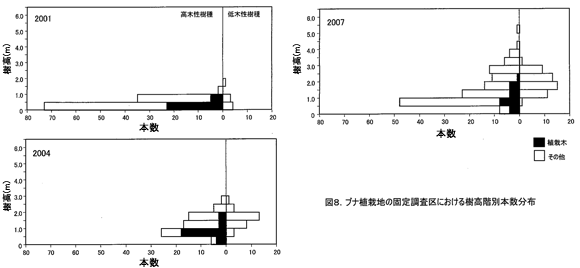
●種組成の変化
ブナ林に多く生育している林床生草本とブナ林を構成する木本種など10種が、2004年から新たに出現した。
ススキの優占度増加による被圧のため、ナギナタコウヨウジュ、オオバコ、トウバナなどの路傍雑草的な草本種や先駆的性質の強い木本種は消失や優占度が減少している。
3.まとめ
ケヤキ植栽地、ブナ植栽地に共通した傾向は以下の通り。
1) |
多量の天然生稚幼樹の発生 |
2) |
樹種による生存率の差異 |
3) |
エゴノキ、ホオノキの良好な成長 |
4) |
放置枝条終焉への樹木の集中 |
植栽木の成長だけにこだわらず、天然生稚幼樹を育成することで、二次林的な樹種構成の森林を成林させることを目標にするのが妥当。
ケヤキ植栽地とブナ植栽地のクサギ生育状況より、クサギの発生は高木性樹種の生育を阻害するとは言えず、いち早く樹冠をつくり、林床性植物の生育場所を確保した点で、重要な役割を果たしているかもしれないと言える。
天然生樹木の定着に放置枝上が寄与したのは、伐根に付着していた土に含まれていた種子が発芽したことが要因と考えられる。
放置枝条部分では樹林化が進行しているが、それ以外ではススキの繁茂が著しく天然生樹木の生育量が少ない。周囲の林冠が発達してススキが被圧されるまで、樹木の大幅な増加は難しい。また、放置枝条の上に定着した樹木は枝条の分解に伴い根が浮き、根返りをおこす恐れがある。ススキ優占部分の管理と根返り対策が今後の課題。