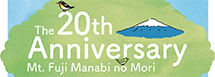自然あふれる富士山2合目の「まなびの森」フォレストアークから
四季折々のようすやボランティア活動についてお伝えします。
みなさん是非「まなびの森」へ足をお運びください。
お待ちしております。
富士山「まなびの森」フォレストアーク副館長・管理人
沢田明宏
2026年の始まりです。
昨年12月は比較的暖かい冬でしたが、新年を迎えて10日ほど経ったころから冷え込みが厳しくなってきました。1月20日過ぎると今シーズン一番の雪が降りフォレストアークも白く雪化粧しました。
2000年から続けているモニタリング調査の内、鳥獣生息調査は「日本野鳥の会 南富士支部」の皆さんに年4回(1月、2月、5月、6月)お願いしています。1月、2月は冬鳥の調査が主な目的です。1月12日の調査では、アトリ、ツグミ、ウソ、シメなどの冬鳥とエナガ、ヤマガラ、アカゲラなどの常連など合わせて21種の野鳥が記録されました。
2023年に植樹をした木の枝にコロンとしたものが刺さっているのが見えます。良く見てみるとコオロギが枝に刺さっています。これはモズの「はやにえ(早贄)」と呼ばれるものです。モズが自分の備蓄食ためと言うのがこれまでの有力説でしたが、最近は恋愛成就の栄養食のためと言われています。「はやにえ」を多く準備したモズの雄は春先にそれを食べて栄養補給を良くすることで様々な啼き声ができるようになってパートナーに強くアピールできるのだそうです。モズは漢字で「百舌鳥」と書くように、昔から様々な啼き声を持つ鳥として知られていました。そんなモズの一面が垣間見えました。
-

朝陽を浴びて輝くように美しい富士山は2合目あたりまで白く雪化粧しました
-

今シーズン一番の雪化粧をしたフォレストアーク
-

「野鳥の会 南富士支部」の皆さんによる鳥獣生息調査
-

陽の光を浴びてキラキラと輝くように見えるヤドリギの黄色い実
-

モズの「はやにえ(早贄)」
冬枯れの森はドラマが少ないです。ただ、葉を落とした森は、遠くまで見通せることが何よりの魅力です。そんな中では、冬の渡り鳥であるアトリやツグミの仲間が群れをつくり、啼き交わしながら飛びまわっているのを見ることができます。
「まなびの森」の「主の樹」と呼んでいるシナノキが7月にたくさん花を咲かせたことをご紹介しました。花が咲けば、その結果として実がなります。今年はシナノキの種がたくさん林床に見られます。花は5~10が小さな塊になって咲きますが、その花序と呼ばれる房の根元にはヘラ状の苞(総苞片)があります。種が実ると、総苞片をくっ付けた形で種がクルクル、フワフワと舞いながら遠くへ飛んでいきます。総苞片がまるで竹トンボの羽のような役割を果たしています。シナノキが遠くまで種を飛ばして子孫を残そうとする作戦が良くわかります。
フォレストアークの近くに小さな水場があり、そこではいろいろな野鳥や動物たちが集まり、水浴び、水飲みをしながら、興味深い出来事を繰り広げています。近くに設置しているセンサーカメラがその様子を捉えていますが、時折センサーカメラの箱の上にも動物たちの活動の痕跡が残されています。今回は箱の上にテンの糞が残されていました。ツルマサキかツルウメモドキの赤い実をたくさん食べたのでしょう。糞も赤色に染まっていました。
また、フォレストアークから直線距離で500~600mの場所に割りと大きなヌタ場があり、そこにもセンサーカメラが2個設置されています。今回、ヌタ場にやって来たツキノワグマがセンサーカメラから発せられる赤外線に興味津々で覗きこんでいるシーンが捉えられました。カメラ箱の上にはクマが前足で擦った泥汚れが残っていました。
2025年は終わろうとしています。今年1年間ご愛読ありがとうございました。来年も色々な角度から「まなびの森」をご紹介できたらと思います。
-

シナノキの種とその総苞片(赤円内) この総苞片が竹トンボの役割を果たす
-

水場に設置しているセンサーカメラの上にあったテンの糞
-

ヌタ場に設置しているセンサーカメラの箱の上に残っていた泥汚れ(赤円内)
-

別のセンサーカメラが捉えたツキノワグマがセンサーカメラに興味深々な瞬間
-

ヌタ場のセンサーカメラ2つ 向かって左が近景、右が遠景 今回は近景カメラ箱に泥汚れが付いており、それを遠景カメラが捉えていた
-

仕事納めの朝に見られた雪化粧が美しい富士山
今年の紅葉は色づきが悪いと先月書きましたが、11月になってようやくヤマモミジやイタヤカエデ、ヒナウチワカエデが色づいてきました。ただ、やはり例年と比べると黄色味が強い色づきとなっています。いつもの年であれば、きれいに赤く色づくヤマモミジやヒナウチワカエデが黄色がかった薄いピンク色に紅葉しています。例年に比べて森に赤色が少なく、黄色が多い感じです。夏~秋の高温が影響しているのでしょうか。
ただ、その中で鮮やかに赤く色づいている樹があります。メグスリノキです。3枚の複葉で一見分かりにくいですが、れっきとしたカエデの仲間です。名前のとおり昔から葉や小枝を煎じた液体を眼病の洗眼に使ったそうで、別名チョウジャノキ(長者の木)とも呼ばれています。現代の科学的分析でもその薬効が確認されています。
富士山の初冠雪から何度か降雪を繰り返し、ある日の朝には5合目まできれいな雪化粧となりました。山頂付近では強い風に雪が舞い上がって、雪煙が見られました。
小春日和の続く日々があり、森の中では11月になってもキノコが多く見られました。朽ちかけた切り株にはホコリタケが群生しており、一箇所にこれほど大量に発生している様子は初めて目にする光景でした。別の朽木にはイタチタケが群生していました。イタチタケは傘の色がイタチやテンの体色に似ているのが名前の由来だと考えられます。傘の縁には白い綿毛のような被膜があるのが特徴ですが、脱落しやすいので見分ける時には注意が必要です。また、色鮮やかなヒイロチャワンタケも見られました。
森の樹々は葉をすっかり落として、冬支度が整った様子です。青々とした葉が残っているのは常緑のツルマサキ、茶色い葉を残しているのはチドリノキと一部のブナです。
2025年も残すところあと1ヶ月となりました。
-

10月の初冠雪から何度か雪化粧し、5合目あたりまで雪に覆われた富士山
-

青空に黄葉が色鮮やかに映えてます
-

今年はヒナウチワカエデが黄色く黄葉
-

例年、きれいな紅葉を見せるコハウチワカエデも黄色みが勝っています
-

今年の「まなびの森」で一番きれいに紅葉したメグスリノキ
-

きれいな紅葉のメグスリノキの落葉 形は変わっていますが、カエデの仲間です
-

朽ちかけた切り株からホコリタケが大群生しました
-

森のあちらこちらでホコリタケがたくさん発生しました
-

色鮮やかなヒイロチャワンタケ
-

真っ黒いマメサヤタケ
-

傘の縁に白い被膜をもつイタチタケ 名前の由来は恐らく傘の色がイタチの体色に似ているからでしょうか