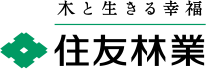- ホーム
- 企業・IR・ESG・採用
- サステナビリティ
- トップコミットメント
トップコミットメント
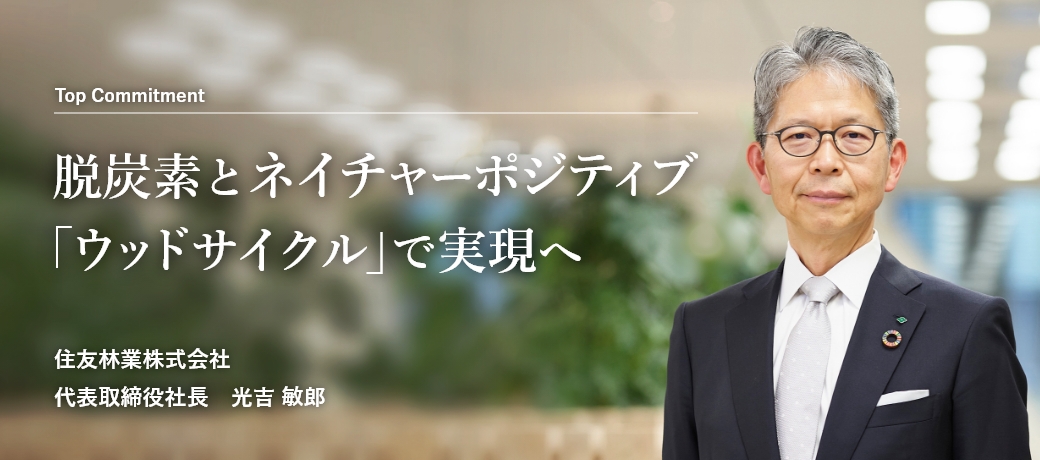

過去の常識が通用しない不透明な時代に
「観測史上一番暑い夏」。これまでに何度も耳にしたフレーズですが、2024年は通年で観測史上最も高い気温を記録し、気候研究で著名な米国の研究機関バークレー・アースによると産業革命前と比べ1.6℃上回ったそうです。気温上昇とともに激甚化する自然災害は常態化しつつあり、企業経営に大きな影響を及ぼすだけでなく、人々の日常生活も脅かしています。
国内では、2024年元日に発生した能登半島地震に始まり、大雨による土砂流出など人的被害を伴う過去例をみない規模の災害が各地で発生、2025年に入ってからは乾燥少雨の影響により岩手県大船渡市をはじめ大規模な森林火災が頻発しています。また3月28日、ミャンマーで発生したM7.7の地震では多くの人的被害、インフラ被害が発生し、世界からの支援が待たれています。住友林業グループは、 現地で医療活動を行う日本のNGOに支援を行いました。
未曾有の「選挙イヤー」だった2024年を経て、多くの国や地域で自国優先を掲げる政党、候補者が勝利し、相互に協力・依存する形で発展してきたグローバル経済は大きな転換点に直面しています。サステナビリティ関係の規制も厳格化の方向かと思えば、EUではこの4月にオムニバス法が可決され、企業サステナビリティ報告指令(CSRD)の対象企業縮小、適用時期の延期、報告基準の簡素化、合理的保証への移行中止などが盛り込まれました。当社は2022年、Sumitomo Forestry Europe Ltd.を英国ロンドンに移転しており、EU域内に拠点がないことからCSRD規制対象ではありません。しかしながら、投資家からみて開示時期や内容に遜色がないよう常に最新動向を注視していますし、今こそ中長期の視点に立ちサステナビリティ経営を粘り強く追求していくことが重要になっていると感じています。
「ウッドサイクル」を通じた社会全体の脱炭素化に向け手ごたえ
SDGsの目標年でもある2030年を見据え2022年2月に公表した長期ビジョン「Mission TREEING 2030」は、方針の一つに「森と木の価値を最大限に活かした脱炭素化とサーキュラーエコノミーの確立」を掲げています。昨年終了した3年間の中期経営計画Phase1では当社グループのバリューチェーン「ウッドサイクル」の森林、木材、建築、エネルギーの各分野でCO2吸収・固定量を増やす施策に焦点を当て取り組んできました。
「森林」分野では、第1号森林ファンドによる森林資産の取得が順調に進みました。当社が従来から保有・管理していた森林面積と合わせると2024年度末で36万5,000ヘクタールに達しました。「木材」分野でのウッドチェンジの推進では、福島県いわき市で木材コンビナートの第一弾となる株式会社木環の杜を立ち上げ、2026年春の商業生産開始を予定しています。
木は光合成により二酸化炭素を吸収し伐採された後も大量の炭素を固定しており、木造は脱炭素設計のスタンダード化のカギとなります。「建築」分野では、戸建住宅の木造化・長寿命化を推し進め、国内外の年間住宅供給戸数は約2万5,000戸となりました。非住宅建築では米国、豪州、英国、日本で中大規模オフィスなど木造化の実績も積み上がっています。
事業活動における脱炭素化においては、温室効果ガス排出量削減で、SBTガイダンスに則り、新たに2050年ネットゼロ目標、FLAG(森林・土地・農業)セクター目標の認定を2024年11月に取得。同時に2030年までの短期目標についても、従来の目標「2017年度比54.6%削減」から「2021年度比42%削減」に上方修正しました。中期経営計画Phase1終了の2024年は、2018年にSBT認定を受けてから2030年目標への折り返し点でもありましたが、紋別バイオマス発電所での石炭混焼率を5%台まで引き下げたことなどを主要因に目標を大幅に達成。同時に、RE100における再生可能エネルギー導入目標についても、設備投資や卒FITオーナー向け電力サービス「スミリンでんき」の提供などを通じ、再エネ導入率41.4%となりPhase1の目標を達成しました。
一方で、サーキュラーエコノミーの実現に向けた省資源・リサイクルにおいては、住宅事業できづれパネル、屋根スレート、サイディングのプレカット化に取り組んだものの、産業廃棄物最終処分量はPhase1の3年間で5.1%削減にとどまり、リサイクル率も95.1%と、いずれも目標は未達となりました。Phase2の3年間で取り組みを加速してまいります。
「Mission TREEING 2030」は次なるステージへ
長期ビジョン「Mission TREEING 2030」では、当社が率先してバリューチェーン「ウッドサイクル」を循環させることで、生物多様性も含めた地球環境の保全、人と社会への貢献、経済価値の創出を推進し社会全体の変化につなげていくことを目指しています。2024年までのPhase1の実績も踏まえ、この2月「Mission TREEING 2030 Phase2」発表にあたり、2030年の目標数値を経常利益2,500億円から3,500億円へ、森林の保有・管理面積は50万ヘクタールから100万ヘクタールへ、海外での提供住宅戸数は5万戸から6万5,000戸へとそれぞれ引き上げました。
2024年9月、豪州最大のビルダーであるMetriconグループの持分51%を取得したことで戸建住宅着工戸数は年7,000戸を超えることとなり、圧倒的なシェアを確保しました。ビクトリア州では2023年に住宅のエネルギー効率基準が強化され新築戸建住宅への太陽光パネル設置などが義務化されていますが、規制適用前からいち早く省エネに取り組んできたHenleyグループとともに脱炭素設計推進をけん引してまいります。
日本国内でも改正建築物省エネ法が2025年4月からいよいよ施行されました。木造戸建住宅を含む全ての建築物において省エネ基準への適合が義務化され、2050年のカーボンニュートラルに向け建築分野の脱炭素化が加速します。2024年11月には内閣官房主導により、原材料から建築資材、設備、設計、建設と多岐にわたる産業分野の監督各官庁を横断する形で「建築物のライフサイクルカーボン削減に関する関係省庁連絡会議」が設置され、居住時だけでなくライフサイクルでの脱炭素化が推進されています。住友林業グループはエンボディドカーボン※の削減に向け、One Click LCA、エコラベルEPDの普及促進など建築のバリューチェーン全体でのソリューション提供を行ってきましたので、「Mission TREEING 2030」のビジョンと国の政策が合致していることに意を強くしています。
※建築資材の原材料調達から、加工、輸送、施工・建設、修繕、廃棄・リサイクルに際して発生するCO2
ネイチャーポジティブへ、森林の価値評価が重要な課題
Phase1で重点的に取り組んできた脱炭素に加え、Phase2からは2030年までに自然の損失を止め、反転させる「ネイチャーポジティブ」への貢献も加速するべく、この2月ネイチャーポジティブ・ステートメントを策定しました。具体的な取り組みとしては森林の価値を正確に評価することが第一歩です。森林は、生物多様性保全に加え、大気、水、土壌といった生態系を構成していますが、これまでは生産される木材の販売価格でしか価値が評価されてきませんでした。森林由来の炭素クレジットの登場によって、「炭素吸収固定」という第二の価値が顕在化しましたが、清浄な空気、水源涵養、土砂災害防止など「正の外部経済」は社会的に大きな価値をもたらしているにも関わらず、その評価方法が定まっていません。評価指標が経済価値へと正当に変換され、持続可能な森林経営を行うインセンティブを示し、投資を呼び込み、技術革新の促進につなげることが重要です。住友林業は、WBCSD(持続可能な開発のための世界経済人会議)や、2023年に新しく設立されたISFC(持続可能な森林国際連合)のメンバーとなり、他の森林企業と協業しながら新しいルールづくりにチャレンジしています。森林、木材、建築、エネルギーの「ウッドサイクル」を回していくことで共通の社会課題解決に取り組んでまいります。
激変する事業環境に対応できる組織体制・人財育成を
更なるグローバル化の進展やバイオリファイナリーなど新たな事業領域への挑戦、既存事業の変革が求められている中、その舵取りに重要となるのは人と組織です。これまで進めてきた「SAFETY FIRST(セーフティファースト)」、健康経営に加え、2024年4月には「住友林業グループ DEI宣言」を制定し、新人事・評価制度を導入しました。人財育成・エンゲージメントの向上を通じ、コンプライアンスの徹底、多様な社員一人ひとりが健康でいきいきと活躍できる包摂的な組織・職場づくりを進めます。
住友林業は1691年の創業以来、住友の事業精神である「自利利他公私一如」の考え方で自社のみならず社会全体への価値提供を目指してきました。住友林業グループ社員が一丸となり、国内外多くのビジネスパートナー、ステークホルダーとともに、持続可能で豊かな社会づくりに貢献してまいります。
- ホーム
- 企業・IR・ESG・採用
- サステナビリティ
- トップコミットメント