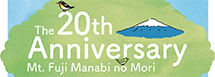モニタリング活動
植生調査 2010年度報告書
1.目的
富士山南麓では1996年(平成8年)9月の台風17号により大規模な風倒被害が発生し、壮齢ヒノキ林を中心に約90,000m3が被害を受けた。富士山「まなびの森」事業計画では、この風倒被害跡地に広葉樹を中心とした在来樹種を植栽することによって、早期に自然林を復元することを目指している。
本調査は、「まなびの森」区域内での台風による風倒跡地の森林の回復および変化について、モニタリングをおこない、自然林の早期再生のための管理・施業方法に関する情報を得ようとするものである。
2010年度の調査では、2000年から2001年にかけて群状植栽地に設置した国定調査区2ヶ所の追跡調査をおこなった。この結果を前回までの調査結果と比較することによって、過去約10年間の植生変化および森林の再生状況を明らかにした。
(1) ケヤキ植栽地
1999年に植栽がおこなわれた場所に、翌2000年に設置した調査区であり、植栽後11年が経過している。面積は20m×20mの400m2で、10m×10mの区画に4区分されている。調査区内には主としてケヤキが植栽されているが、コナラやイロハモミジも少数含まれている。ここでは、2000年に毎木調査、2001年に種組成の調査がおこなわれ、2003年と2007年に同じ項目が再度測定された。今回の調査は3度目の追跡調査となる。
(2) ブナ植栽地
2001年に植栽がおこなわれた場所に、植栽直後の2001年に設置された調査区であり、植栽後9年が経過している。ケヤキ植栽地と同様、面積は20m×20mの400m2で、10m×10mの区画に4区分されている。調査区内にはブナのみが植栽されている。ここでは、2001年に毎木調査、2002年に種組成の調査がおこなわれ、2004年と2007年に同じ項目が再度測定された。今回の調査は3度目の追跡調査となる。
各固定調査区の調査実施年
*種組成の調査のみ実施
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.調査方法
2010年は各調査区において、以下の調査をおこなった。
(1) 毎木調査
調査区内に生育している樹木について、植栽、非植栽にかかわらず、各個体の樹高および根元直径を測定した。高木性樹種については樹高30cm以上、低木性樹種については樹高130cmの個体を調査対象とした。樹高は検測棹をもちいてcm単位で、根元直径はノギスを用いてmm単位で計測した。また、個体識別のためにナンバーテープをつけ、位置図を作成した。各個体の樹高および根元直径を測定した。
(2) 植生調査
10m×10mの区画を単位として、植物社会学的な方法による植生調査をおこなった。これは、出現するすべての植物をリストアップして、それぞれの種の優占度および郡度を判定するものである。優占度・郡度はBraun-Blanquet(1964)の判定基準にもとづき、+、r、1、2、3、4、5の7段階で評価した。
3.調査結果
(1) ケヤキ植栽地の再生状況
クサギが優勢な時期を過ぎ、キハダ・ミズキ・エゴノキ・ホオノキなどによる林冠が形成されつつある。植栽したケヤキの成長量も回復してきた。
現時点で植栽したケヤキ20本のほかに、ミズキ、キハダ、エゴノキを中心に64本の高木性樹種の稚樹が生育している。上記の3種にホオノキを加えた4種は成長が良好であり、一部は約7mに達している。また、根元直径も大きなもので10cmから15cmに達しており、これらの樹種が将来、林冠を形成していくと考えられる。しかし、その分布は放置枝条周辺に偏っており、それ以外ではケヤキの植栽木を育成していくことが必要である。低木層で優占していたクサギは樹高成長が頭打ちになり、枯死木も増えて、衰退のきざしがみられる。今後数年のうちにクサギの枯死が進めば、他の樹木の成長に大きな影響が現れるかもしれない。種組成としては、風倒被害以前から生育していたとみられる低木性の樹種や、林床生の草本が豊富に残っているため、林冠が閉鎖すれば草原生、陽地生の種が消えて、種組成が森林に近づいていくことが期待できる。ただし、シカが採食しやすい大型の草本が減少したり、シロヨメナ、フタリシズカなどの不嗜好性植物が増加したりするなど、シカの採食の影響を受けることは免れないであろう。
(2) ブナ植生地の再生状況
ススキの繁茂により、植栽したブナや、キハダ・ミズキは衰退。エゴノキ・ヒメシャラ・ホオノキが林冠構成種の候補だが、回復には時間がかかりそうだ。
植栽したブナ20本のほか、エゴノキやヒメシャラが多く生育している。エゴノキに加えて、数は少ないがホオノキの成長が良く、この2種が初期の林冠構成種の候補である。当初、個体数が多かったキハダとミズキは激減しており、後から増加したエゴノキやヒメシャラにとって代わられている。ここでは、ススキの繁茂が著しく、主にキハダやミズキはススキによる被陰が原因で枯死したと考えられる。エゴノキやヒメシャラは、葉のサイズが小さく、横枝をそれほど広げずに上方に伸長する傾向があり、ススキともある程度共存できるようである。植栽したブナの大半は成長が停滞しており、やがてススキによる被陰で枯死する可能性が高い。この調査区ではススキの旺盛な成長が衰える様子はなく、当面はススキが優占した状態が続くと考えられる。そのため、ケヤキ植栽地に比べると森林への回復は時間がかかるであろう。また、ススキは大量のリターを地表面に蓄積するため、林床の種組成にも影響を及ぼす。特に小型の林床生草本は、リターに覆われると成長できなくなるため、しだいに種組成の単純化が起こることも考えられる。
ケヤキ植栽地の固定調査区の現況

林内