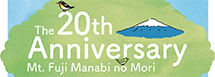自然あふれる富士山2合目の「まなびの森」フォレストアークから
四季折々のようすやボランティア活動についてお伝えします。
みなさん是非「まなびの森」へ足をお運びください。
お待ちしております。
富士山「まなびの森」フォレストアーク副館長・管理人
沢田明宏
今年はトレール沿いの立枯れ木の伐採が仕事始めとなりました。昨年末に森林管理署と相談の上、トレールに近い立枯れた樹木は危険と言う事で森林ガイドの方に協力していただき伐採しました。また、別の日にはホールアースの方々に協力していただき、トレール途上の深く抉れた涸れ沢、通称「まなびの森」キャニオンに木製の橋を架けていただきました。これで今年も皆さんに安心して「まなびの森」を歩いていただくことができます。
1月第2週に冬鳥の調査のため「野鳥の会」の皆さんによる「鳥獣生息調査」が行われました。野鳥の種数は14種と少なかったです。そんな中で、特別に目立ったのがゴジュウカラでした。森の中のあちらこちらで「フィーッ、フィーッ」と良く通る啼き声が聞かれ、「今日はゴジュウカラの大合唱会だね」などと口々に話していました。
ゴジュウカラ(体長 13.5㎝)は青灰色をしていて、尖った嘴を持ち、嘴から目元まで黒くアイシャドウのあるスズメ(体長14.5㎝)より少し小さい鳥です。野鳥の中で唯一木の幹を下向きに下りことができます。素晴らしい身体能力を持った鳥と言えます。
1月末には、昨年一年間の「まなびの森」での活動を実地に踏査しながら振り返り、今年の活動に活かすための「活動状況調査」を行いました。日中の最高気温も氷点下と言う真冬日の厳しい寒さでしたが、森の中を10人で歩きながら今年の課題などを確認しました。トレールの一番高い場所にある通称「海の見えるケヤキ」からは冬枯れで見通しの良い森から駿河湾越しに伊豆半島も見えます。
私にとってこの冬は4度目ですが、例年に比べ格段に厳しい寒さが続いています。「フォレストアーク」の建物の中に置いている手洗い用の水がドンドン凍っています。こんなことは今までにありませんでした。
2月は更に厳しい寒さになるのではないかと、内心ヒヤヒヤして春が待ち遠しいです。
-

トレール沿いの立枯れ木を伐採
-

トレールを通せん坊していた倒木も伐ってもらいました
-

トレールのキャニオンに橋が完成しました
-

キャニオン橋架けにご協力いただいたホールアースの皆さん
-

真冬日の中、活動状況調査を行いました
-

その途上、キャニオン橋の渡り初めをしました
-

橋の向こう側でもテープカットをしました
-

凍てついた落ち葉からも霜が
-

苔むした樹の幹が薄っすら雪化粧
-

「海が見えるケヤキ」から眺める駿河湾と伊豆半島
-

巨木の1つ「海が見えるケヤキ」
-

ゴジュウカラは頭を下にして樹の幹をして下りることができます ※ 別の場所で野鳥の会 南富士支部の方が撮影されたものをご厚意で提供していただきました
冬になると存在感を増すのは先月のツルマサキだけではありません。高い樹の上を見上げると、丸いボール状の塊が見られます。ヤドリギです。高い場所にあるので、葉や実を見ることはほとんどありません。強い風に煽られたのでしょうか、たまたま林床にヤドリギの枝が落ちていました。規則正しく二股に枝分かれし、その真ん中に黄色い実を付けています。この実は野鳥の大好物ですが、ヤドリギには彼らの巧みな戦略があります。種の周りにはネバネバの粘液があり、鳥の腸内で消化されることなくスルッとお尻へ出てきます。そして、その粘液に守られたヤドリギの種はそのまま他の樹の表面にくっつき芽生えてきます。ヤドリギは樹に居候して水分はもらうようですが、光合成は自分で行っているそうです。
12月初旬に、富士宮市主催の自然観察会(もともと9月に予定されていたが、台風で延期)が開催されました。『冬に自然観察会なんて…』と半信半疑で参加された市民の皆さんもプロのガイドの奥深い知識を絶妙なトークで楽しみながら、見通しの良い森を歩き、新しい発見と知識を持ち帰っていただけました。冬には「冬の森の魅力」があると実感していただけてほんとうに良かったです。
「まなびの森」より標高が高い場所にはシナノキが沢山生えています。そして、それは「まなびの森」の「長老シナノキ」よりも更に迫力ある樹形となっています。
また、「まなびの森」の少し東側には不思議な樹形のケヤキがあります。まるでポパイが力こぶを自慢しているようにも見える通称「ポパイのケヤキ」です。どうしてこんな樹形になったのか色々想像してみるだけでも面白いです。そして、手で触れるとケヤキのパワーをもらえるようです。
2022年もいよいよ終わりとなります。今年も1年間ご愛読ありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。
-

冬の樹を見上げるとよく見られるヤドリギ 黄色い実は野鳥の好物
-

ヤドリギの巧みな戦略でマメザクラの枝に芽生えが出てきました (3年目の芽生え)
-

富士宮市主催の観察会の参加者とガイド2名(両端)
-

「まなびの森」より高い標高のシナノキは「長老シナノキ」よりもさらに迫力満点
-

「まなびの森」の少し東側にある不思議な樹形のケヤキ、通称「ポパイのケヤキ」
■11月管理人日記
今年の11月は雨が少なかったです。特に、前半は連日の晴天続きでした。気温は低いですが、日向は小春日和の暖かさが嬉しかったです。そんな暖かさに誘われたのでしょうか、1時間ほど森の巡回をして戻ってくると「フォレストアーク」の裏玄関に出掛ける前にはなかった瑞々しい糞が落ちていました。色がやたら緑色ですが、大きさと形、そして臭い(少しナフタリン臭)からするとテンの残していったものらしいです。
ウラジロモミの幹に細いキズが何本も付けられていました。これは、雄ジカの角研ぎの痕です。幹に擦りつけて先を尖らせるように研いでいるのです。
斜めから差し込む太陽光に照らされ、イタヤカエデの黄色が鮮やかに輝いています。冬枯れになる前の艶やかさを誇っています。
葉を落とした後に目立つようになるのがツルマサキです。ブナやケヤキ、カエデの仲間に付いているツル性の樹木で、常緑なので冬には存在感が増します。ツルマサキは赤い実を沢山つけるので、小鳥たちの格好のエサにもなります。ヤマガラ、シジュウカラやゴジュウカラなどが特に好んで啄んでいます。
今年最後の自然体験教室を無事終えました。寒い日でしたが天気に恵まれ、子どもたちは元気に森を歩きながら思い思いの落ち葉を拾い、それをフレームに挟んで空にかざして見ると「森のステンドグラス」が完成します。「一つとして同じ色・形の葉はない」と言う多様性を知る環境学習です。
森は冬枯れで見通しが良くなり、晴れた日には駿河湾や伊豆半島も見える冬本番を迎えようとしています。
-

「フォレストアーク」の裏玄関先の真新しいテンの糞
-

ウラジロモミの幹でシカが角研ぎした痕
-

鮮やかな黄色に色づいたイタヤカエデ
-

赤いツルマサキの実
-

今年最後の自然体験教室は寒い晴天の下で
-

子どもたちが拾った落ち葉で「森のステンドグラス」が完成