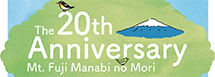自然あふれる富士山2合目の「まなびの森」フォレストアークから
四季折々のようすやボランティア活動についてお伝えします。
みなさん是非「まなびの森」へ足をお運びください。
お待ちしております。
富士山「まなびの森」フォレストアーク副館長・管理人
沢田明宏
■10月管理人日記
10月になると冬の訪れを告げる雪虫がフワフワと飛び、丸いハート型をしたカツラの葉が甘いカラメルの薫りをフォレストアーク周辺に漂わせ始めます。カツラの甘い薫りは葉が緑のあいだは気まぐれに時たまですが、黄色く色づきが進むに連れて毎日のように薫るようになります。
アズマヤマアザミがかわいらしい花をつけています。山の中で作業をしていると足にチクチクと突き刺さるものがあります。アズマヤマザミの葉の鋭いトゲがズボンを通り抜けてくるのです。チョッと憎らしいアザミですが、花は大層かわいらしいです。
強い風に煽られて枝が折れたのでしょう、ウラジロモミの球果が落ちていました。持ってみるとずっしりと重いです。ウラジロモミはちょうど「まなびの森」のある標高1,000mあたりから1,700mあたりまで分布しています。「まなびの森」のウラジロモミは国有林が植林したものです。ウラジロモミの巨木は諏訪神社の「御柱」に利用されていることで有名です。
苔むした樹にヌメリスギタケが発生しています。ナメコに似た食感の美味しいキノコです。そして、地面に半分埋もれて朽ちかけたホオノキの実から黒く尖った堅い棒状のものが生えています。ホオノキの実から生えるホソツクシタケと言うキノコです。
10月後半になるとブナやイタヤカエデが黄色く、オオモミジやイロハモミジは紅く色づきます。太陽高度が低いので、斜めに射す日差しにキラキラと森が鮮やかに彩られます。
2ヶ月近く通行止めとなっていた「富士山スカイライン」が開通し、小学生が訪れ、社員ボランテイア活動もできるようになりました。
でも、季節は寒く静かな冬へと季節が移っていこうとしています。
-

アズマヤマザミ(東山アザミ)の花
-

ウラジロモミの球果(マツボックリ)は上向きに
-

ヌメリスギタケが苔むした樹に発生
-

ホオノキの朽ちかけた古い実から発生するホソツクシタケ
-

緑から少しずつ紅葉が進んでいく(ブナの葉)
-

朝の陽ざしに照らされた巨木ブナ
-

青空にオオモミジの黄色と赤のグラデーションが映える
-

葉の切れ込みが細かいコハウチワカエデは日差しに照らされてレースのように
■9月管理人日記
9月に入って気温が下がるにつれて森のあちらこちらでさまざまなキノコが生えてきます。落ち葉の上にはハタケシメジ、倒木にはヒラタケやヌメリツバタケが見られます。
ハタケシメジやヒラタケ、ヌメリツバタケはたくさん生えるので、見つけるのが楽しくなります。ハタケシメジはスーパーにも並ぶ「ブナシメジ」を大きくしたようなキノコで、味も香りも抜群です。ヒラタケも美味しいキノコですが、気をつけなければいけないのが良く似た毒キノコのツキヨタケです。ツキヨタケの名前は暗闇でボーッと光るからです。ただ、私はまだ光っている状態を見たことはありません。ツキヨタケは半分に切ると軸の付根に黒いシミがあるので、注意すれば割りと簡単に見分けることができます。
林床に青白い俯きかげんの花が咲いています。ギンリョウソウモドキ(別名 アキノギンリョウソウ)という葉緑素を持たない寄生植物です。ある種の菌根から栄養を得ているそうです。初夏に咲くのはギンリョウソウ(別名 ユウレイバナ)といい、別の種類です。
古い枕木の上に変わったキノコが生えています。まるでハリネズミが丸まっているようです。名前はヤマブシタケ、山伏がその装束の胸のところにつけている「梵天」という飾りに似ていることから付いた名前です。このヤマブシタケも最近時々スーパーの店頭に並んでいます。
さて、「まなびの森」の「主の樹(ぬしのき)」とも称せられる「長老シナノキ」の洞の中に何か白いものがたくさん見えます。何だろうと覗き込んでみるとたくさんのキノコが生えていました。ハラタケの仲間です。まさに、「木ノ子」という絵になっていました。この洞は色んな動物(例えば、タヌキやキツネ)のねぐらにも利用されているので、有機物が蓄積されているのかも知れません。その有機物をキノコが分解しているのではないかと想像されます。
古い倒木には色々なキノコが次々と発生します。その中でも色鮮やかなサーモンピンクのキノコが生えてきます。その色合いからマスタケと名前がついたサルノコシカケの仲間です。
気温が下がってきて昆虫は少なくなりましたが、大きなチョウがヒラヒラと飛んでいます。アサギマダラです。アズマヤマアザミの花にとまって一生懸命に吸蜜しているので写真に収めることができました。アサギマダラは翅を拡げると10㎝もある大きなチョウで、海を渡って遠く直線距離で1,500Kmも飛んでいくことで知られています。この写真のチョウはどうでしょうか。
夏の間のサンショウの実は濃い緑色でしたが、秋の気配が深まるにつれて色づき始め、紅葉より先に真っ赤になりました。
森の中でショッキングな光景に出遭いました。メスのシカが一頭死んでいました。原因はわかりませんでしたが、たぶん死後3~4日経っているだろうとのこと。どうすることもできずにそのまま放っておかざるを得ませんでした。2日後に再び見に行くと、シカの死骸が見当たりません。どうしたことかと、近づいてみると無数のウジが群がっていてほとんど白骨化しています。更に、2~3日経ったころには完全に白骨と化していました。自然の中で有機物が分解される速さとその強さ、生命の循環の見事さと自然の過酷さ、そしてある種の無常さを見せつけられた思いです。
「まなびの森」への唯一のアクセスである「富士山スカイライン」が大雨の影響で8月中旬以来通行止めとなっているため、いろいろなイベントが延期や中止となっています。徐々に復旧工事も進んでおり、きっともうすぐ子供たちの元気な姿と笑い声が紅葉の森に響く日が戻ってくるでしょう。
-

落ち葉の上にハタケシメジが
-

倒木にビッシリ生えたヌメリツバタケ
-

食用キノコとしてもスーパーにも並ぶヒラタケが倒木に沢山発生
-

そのヒラタケと良く間違われる毒キノコ、ツキヨタケ
-

ツキヨタケは軸の付根に黒っぽいシミが識別のポイント
-

秋に咲くギンリョウソウモドキ、別名アキノギンリョウソウ
-

古い枕木に発生したヤマブシタケ、最近は食用キノコとしてスーパーにも並ぶことが
-

「長老シナノキ」の洞になにか白いものがたくさん見えます
-

中を覗き込むとハラタケの仲間がたくさん発生、まさに「木ノ子」です
-

鮮やかなサーモンピンク色がひときわ目立つその名も「マスタケ(鱒茸)」
-

大きなアサギマダラがアズマヤマアザミの花で吸蜜
-

初夏から青い実を付けていたサンショウが鮮やかに真っ赤に色づきました
■8月管理人日記
今年はモリアオガエルが泡に包まれた卵塊を産む梅雨に大雨が降ることが多く、「フォレストアーク」の周囲では産み付けられた卵塊が雨に打たれて水面に叩き落とされることが続いていました。孵化するまでは水が苦手なモリアオガエルなので、コケの上にオタマジャクシから育った1㎝ほどのモリアオガエルの赤ちゃんを見つけた時はとても嬉しく思いました。同時に3匹の赤ちゃんを見かけました。
オトコエシ(男郎花)と言う花をご存知でしょうか。秋の七草のひとつオミナエシ(女郎花)の親戚にあたる植物で、オミナエシより茎がシッカリして逞しい姿を「男」に譬えたのが名前の由来だと言われています。そのオトコエシの花の蜜を吸いにアブやハチに交じってカメムシがしきりに訪れています。
森の落ち葉の中に細長いマッチ棒か線香花火のようなものをときどき見かけます。掘り出してみると、カメムシの死骸があります。いろいろな虫などから発生する冬虫夏草の仲間で、これはカメムシタケです。昔の人は虫からキノコが生えている姿を不思議がり、冬は虫に、夏は草になっていると「冬虫夏草」の呼び名となったそうです。冬虫夏草はその奇妙な姿もあって漢方薬としても重宝されてきました。
森の中で枯れ葉がガサゴソと音を立てています。ヘビかな、トカゲかな、とよく見るとヒキガエルがいました。冒頭で紹介したモリアオガエルもそうですが、ヒキガエルも水場がないと命を継いでいけません。川も池もない富士山でほんのわずかな水溜りなどを利用して命を繋いでいるかと思うとなんともけなげに思えます。
去年、富士山の周りでもナラ枯れでミズナラなどが沢山枯れました。「まなびの森」もその例外ではなく10本ほどのミズナラが立ち枯れとなりました。ナラ枯れは通称「カシナガ」と呼ばれるカシノナガキクイムシが群がり樹を食い荒らすことで起きます。今年、そのナラ枯れの根元に色鮮やかな朱色をしたカエンタケ(火炎茸)が発生しています。燃え上がる炎のような、宝石サンゴのような形をしたキノコです。カエンタケは致死量がわずかに生重量3gと言われる猛毒のキノコで、日本でも死亡例があります。さらに、カエンタケは素手で触るだけでも皮膚が爛れることがあるそうですので、「うわぁ、きれいなキノコだ」と触ったりしないように気を付けてください。「色鮮やかなキノコは毒、縦に裂けるキノコは食べても大丈夫」と言うキノコの間違った見分け方(迷信)がありますが、カエンタケはその中の大きな例外です。
一方で色鮮やかな食菌があります。タマゴタケです。毒キノコで有名なベニテングタケやテングタケの仲間ですが、タマゴタケはヨーロッパではその美味しさから「王様のキノコ」とも呼ばれています。
そして、日本の有名食菌シイタケを森で見つけました。スーパーでも沢山売っているシイタケですが、森の中では見かけることはほとんどありません。シイタケはもともと熱帯高地が原産地と言う説があります。シイタケの胞子が台風で運ばれてきて日本でも自生するようになったと言うのです。その美味しさから昔からなんとか沢山収穫できるようにと工夫を重ね、木にナタで傷を付けてシイタケが生えやすい場を整えたことから始まり、榾木(ほだぎ)を使った人工栽培に発展し、さらに最近ではオガ屑を固めた菌床栽培に移ってきています。
暑かった夏も8月の終わりが近づいてくると里では稲穂が色づき首を垂れはじめますが、山ではススキが穂を伸ばしていきます。葉先が少しだけ赤や黄色に色づいたモミジの葉が地面に落ちています。秋はもうそこまで来ているようです。
-

モリアオガエルの赤ちゃん
-

秋の七草のひとつ、オミナエシの仲間のオトコエシ
-

オトコエシの花蜜を吸いにやってきたカメムシ
-

マッチ棒か線香花火のように見えるカメムシタケ
-

掘り出してみるとカメムシの死骸から発生しているのがわかります
-

森の中で出会ったヒキガエル
-

猛毒なカエンタケ まるで宝石サンゴのような美しさ、でも触らないで!
-

色鮮やかなキノコは毒キノコ、それは真っ赤な大ウソで とても美味しいタマゴタケ
-

森で見つけた天然のシイタケ
-

紅葉のはじまり 少し色づいたヒナウチワカエデの葉