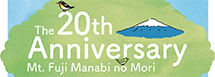自然あふれる富士山2合目の「まなびの森」フォレストアークから
四季折々のようすやボランティア活動についてお伝えします。
みなさん是非「まなびの森」へ足をお運びください。
お待ちしております。
富士山「まなびの森」フォレストアーク副館長・管理人
沢田明宏
■4月管理人日記
暖かい3月から4月に入り、例年より2~3週間早くマメザクラが開花しました。花も葉も小さい、富士箱根地域に見られる在来野生のサクラです。日本には10種類の在来野生サクラが知られています。ヤマザクラ、オオヤマザクラ、カスミザクラ、オオシマザクラ、エドヒガン、チョウジザクラ、タカネザクラ、ミヤマザクラ、クマノザクラ(2018年に新種として登録)、以上9種とマメザクラで10種です。
サクラは自然交配や人工交配が起きやすい種類のようです。また、同じ種類の中でも変化が生まれやすいです。マメザクラ1つをとっても、少し大きな花を付けるもの、花の色が淡いピンク~濃いピンクと樹々によっては変化が見られます。中には白っぽい花で、緑色がかって見えるマメザクラもあります。
森の中でパートナーを求めてシュジュウカラやヤマガラが啼き交わし、メジロのつがいが仲良くマメザクラの花の蜜を吸っていたり、キツツキの仲間のアカゲラやコゲラが樹の幹を突いてエサの虫を探したり。野鳥たちが非常に活発に活動しています。
去年は森じゅうのブナが沢山結実しました。前にもお伝えしましたが、ブナは数年に1回一斉に沢山の実を付けて子孫を残そうとします。ブナの実は美味しいので、リスやネズミ、イノシシなど沢山の野生動物の大切な食糧となります。しかし、大量に結実することで食べ尽くされることなく、子孫を残すことができます。数年に1回、一斉に。ブナの樹はいったいどうやってその時を決めているのでしょうか。ブナの森の不思議の1つです。そのブナのかわいらしい実生が今年は沢山見られます。正に『ブナの大量結実作戦』大成功と言うことになります。
5月から恒例の小中学生対象の自然体験教室が始まります。2006年から始めた社会貢献活動の1つですが、それを前に子どもたちの安全を確保する意味で『スズメバチトラップ』を設置します。「まなびの森」の常連となっている『まじぇる会』の皆さんに手伝っていただき、遊歩道沿いの倒木の近くなどスズメバチが巣を作りそうな場所にトラップを仕掛けていきます。去年設置のトラップは回収して中身を確認するのですが、中には100匹もスズメバチが入っているトラップもありました。
さて、最後にご紹介するのはエイザンスミレ。ちょっと変わった深い切れ込みの葉が特徴的なスミレです。名前の由来は「京都の比叡山で見つかったから」と言うことらしいですが、比叡山以外でもあちこちで見かけます。
-

蕾が赤みを帯びて開花が近づくマメザクラ
-

七分咲きとなったマメザクラの背景は富士山
-

フォレストアークを背景に咲くマメザクラ
-

大きめの花を付けるマメザクラがあり
-

白っぽく、少し緑がかって見えるマメザクラも
-

かわいらしい花を付けるミヤマウグイスカグラ
-

ブナの芽生え
-

1ヶ月ほど早いモミジイチゴの開花
-

自然体験教室の始まる前に『スズメバチトラップ』を設置
-

回収した去年の『スズメバチトラップ』の中身
-

スズメバチだけを並べてみると、1ヶ所でなんと100匹も
-

深い切れ込みの独特の葉をもつエイザンスミレ
■3月管理人日記
3月に入ると標高の高い「まなびの森」でもお預けとなっていた春が訪れました。先月の中頃から暖かい日が多くなり、月が替わったとたんにミツマタの蕾が暖かい雨上がりの朝開きました。オニシバリも小さい花ながら満開となり、ミツマタと共に良い薫りを漂わせています。そして、ヤマネコヤナギ(正式な和名はバッコヤナギ)も可愛らしい綿毛の蕾を見せています。
野鳥も活発に活動しはじめ、シジュウカラやヤマガラが囀っています。遠くではウグイスが啼きはじめましたが、まだ流暢に啼けずどことなく舌っ足らずな啼き方をしていました。それも2週間ほどすると聞きなれたあの「ホーホケキョ」となります。
今年は例年よりズッと暖かく、早春の草花たち、例えばアズマイチゲやヤマエンゴサク、コガネネコノメソウ、ユリワサビが2~3週間早く咲きはじめました。マメザクラも蕾が膨らんで、赤みを増してきて4月初めには開花しそうです。
暖かな陽気に誘われてイノシシも食を求めて活発に行動しているようで、落ち葉の上に縦横にエサ探しの食痕が残されています。
3月30日に去年の活動報告や各調査報告と今年の活動計画をステークホルダーの皆さんと話し合う恒例の「企画懇談会」が新型コロナ感染防止を徹底しながら開催されました。例年板の間である「セミナールーム」で開催するのですが、今年は年度末の忙しい時期にもかかわらず23名と参加者が多かった為密を避ける意味で「フォレストアーク」土間で開きました。皆さまから貴重なご意見もいただきましたので、それを活かしながら今年の「まなびの森」を運営していきたいと思っております。
-

ミツマタが暖かい雨上りの朝、開花
-

2週間ほどで満開となり、辺りが甘い薫りに包まれました
-

ヤマネコヤナギの綿毛に包まれた蕾
-

-

ユリ科のキバナノアマナの可憐な花
-

バイケイソウの新芽
-

3月末には青々としたバイケイソウの群落が出現しました
-

2~3週間早いアズマイチゲの開花
-

早春の花、ヤマエンゴサク
-

シナノキの苔むした所にユリワサビの花が咲いています。
-

イノシシの食痕(この写真ではわかりにくいです)
-

イノシシの食痕ラインに白い点々を付してみました
-

今年の企画懇談会は「フォレストアーク」の土間で開催
-

開会の挨拶を飯塚室長がおこないました
-

初めてご出席いただいた静岡大学の増澤先生がご挨拶
■2月管理人日記
良く「1月往ぬる、2月逃げる、3月去る」と言われます。年明け以来、アッと言う間に月日が経つ様を言い表していますが、2月は日数が少ないので余計に早く感じます。
里ではジンチョウゲが薫り、ウメや菜の花も咲きはじめて早春の気配ですが、「まなびの森」はまだまだと思っていました。ところが、2月とは思えないような暖かな日が続いたこともあってか、オニシバリの花が同じ仲間であるジンチョウゲの薫りを微かに漂わせて咲きはじめました。来月はミツマタも花を開くことでしょう。
寒い朝には大きな霜柱が元気に育っています。そして、薄っすらと雪が降った朝には「フォレストアーク」の周りに置いている木製ベンチの上に小鳥が歩き廻った足跡が残されていました。残念ながら、鳥の種類は判りません。
先月に続いて野鳥の会の皆さんによる鳥獣生息調査が行われました。先月は極寒の日でしたが、今回は暖かな日でした。暖かさに誘われてさぞや鳥の姿や啼き声が賑やかだろう、と期待されましたが、意外にも17種と少なかったです。冬鳥はその年の渡り鳥の来訪場所がどこかと言うことで種類数や個体数の変動が大きいと聞きました。
ある日、クマシデと思われる大きな木が途中で折れて地面に落ちていました。恐らく、くっ付いていたツルウメモドキの蔓の重さに耐えかねたのでしょう。ツルも一緒に落ちていました。クマシデは樹皮がそのままちゃんと付いていましたが、ツルの方は樹皮が剥げてつるつるになっていました。冬の間、食糧難になっているシカが比較的厚みのあるツルウメモドキの樹皮を食べたのでしょう。色々な樹木に絡みついて生きているツルウメモドキの樹皮がシカに齧られているのは目にしたことはないので、折れて枯れたことで樹皮が剥けやすくなったなどの理由でシカが食べやすくなったのだろう、と思われます。
春はすぐそこまで来ていますが、標高が1,110mと高い「まなびの森」ではもう少しの間「お預け」となります。
-

富士山と菜の花畑、早春の景色です
-

15㎜ほどの小さなオニシバリの花、これは雄株で花粉を付けた雄花です
-

-

元気に大きく育った霜柱
-

雪化粧したベンチの上をどんな鳥が歩いたのでしょう
-

クマシデとツルウメモドキが折れて地面に落ちていました
-

-

ツルウメモドキの方は樹皮が齧り取られてつるつるに