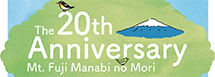自然あふれる富士山2合目の「まなびの森」フォレストアークから
四季折々のようすやボランティア活動についてお伝えします。
みなさん是非「まなびの森」へ足をお運びください。
お待ちしております。
富士山「まなびの森」フォレストアーク副館長・管理人
沢田明宏
7月に入ると気温が高いせいもあるのでしょうか、ヒグラシが一斉に鳴きはじめました。初めは数が余り多くなく涼し気にカナカナカナァ~と、なんとも心地よかったです。それが日を追うごとに数が増えていき、森全体がカナカナカナァ~となってしまい、騒がしいほどになりました。辺りで聞こえるはずの野鳥の啼き声を完全にかき消してしまう勢いに、「過ぎたるは猶及ばざるが如し」の諺どおりだなと痛感したしだいです。
今年もキバナノショウキランがあちらこちらで咲いていました。私が「まなびの森」に着任して6年目になりますが、一度も同じ場所で花を咲かせたことがなく、毎年予測不能な神出鬼没状態です。今年は咲きはじめた非常にフレッシュな花に出遭えたことが嬉しかったです。
今年は概ね気温が高めに推移しているため、草木の花は例年と比べて早めに咲く傾向にあります。が、中にはチョッと遅めに咲くものもあります。ヒメシャラは例年6月終わり~7月初めに咲きますが、今年は7月中旬になりました。サラサドウダンが花を咲かせなかったので、ヒメシャラよお前もか、と気を揉んでいた矢先の開花でした。
先月はコルリのバードストライクに出遭いましたが、今月はクロツグミが軽い脳震盪を起していました。
他にも、トレールの直ぐ隣の地面にスズメバチの巣が見つかりました。虫に詳しい方に調べてもらうとモンスズメバチだと分かり、周辺を立ち入り禁止にしました。ところが、数日後には巣の一部が地上に転がっていました。以前からの経験で、直ぐにスズメバチなどが大好物である猛禽類のハチクマが巣を襲いハチやハチの子を食べたのだと分かりました。
7月最後の土曜日に、社員家族などが参加しての環境学習天然林エコツアーを開催しました。今年は林学博士の西野文貴先生を講師役に招き、植物と植物の関係性から森を知る案内をしていただきました。
-

無葉緑素の寄生植物キヨスミウツボの花
-

ヒグラシの脱皮抜け殻
-

ヒグラシの成虫
-

菌従属栄養の無葉ラン キバナノショウキラン
-

-

ヒメシャラの落花(花ガラ)
-

ガラス窓にバードストライクして脳震盪を起しているクロツグミ
-

モンスズメバチの成虫
-

数日後に猛禽類のハチクマに襲われたモンスズメバチの巣
-

森の中で話をする西野先生 「きこりん」も話を聴いています
-

フォレストアーク内で午後の講義をする西野先生 サクラの葉を湯煎して「芳香水」作りました
毎年、5月末~6月初めに可愛らしい花を咲かせるサラサドウダンが今年は一輪も花を咲かせません。この「まなびの森」に赴任して6年目になりますが、こんなことは初めてです。
さらに、毎年秋に発生するハタケシメジやアカモミタケが6月に発生しました。今年は3月、4月が暑いくらいに気温が高く感じる日が多く、それに比べ5月は気温が低く感じる日が多かったので、キノコたちが秋になった勘違いしたのかもしれません。
そんな中、エゴノキやウツギの白い花が沢山咲き、あたりに甘い薫りを漂わせています。また、サンショウバラが大きなピンクの花をつけ、そこにマルハナバチなどが多く集まって蜜を吸っています。
モリアオガエルがヌタ場や小さな水溜まりを目ざとく見つけてはセッセと泡に包まれた卵塊を産み落としています。
ある日、建物の脇の地面でジッとして動かない青い小鳥がいました。ケガでもしているのかと心配になって近づいて良く見るとコルリでした。どうやら、ガラス窓にぶつかって軽い脳震盪を起したようです。しばらくすると、元気に飛び立っていきました。
林床に白いツバキのような花がボトリ、ボトリと落ちているので近くにヒコサンヒメシャラが花を咲かせているのは良くわかります。でも、高い位置に咲くので咲いている花を見ることはほとんどありません。たまたま、見廻していると手の届くところに一輪咲いていましたので、急いでパチリと写真に納めました。
今年の梅雨は雨の少なくカラ梅雨気味です。それでも、着実に夏に向かって季節は進んでいきます。
-

エゴノキの花は下向きに沢山咲きます 蕾は紡錘形
-

サンショウバラはフォッサマグナ地帯の代表的植物
-

毎年、秋に発生するハタケシメジが6月に
-

同じく秋のキノコ、アカモミタケが発生しました
-

自然体験教室の子どもたちがガイドの話に聞き入ってます
-

産卵を控えているモリアオガエル ※この写真は「まなびの森」とは別の場所で撮影
-

「まなびの森」の小さな水場にモリアオガエルの泡卵塊が産み落とされてました
-

ヌタ場の水際にアナグマの糞が…
-

コルリがフォレストアークのガラス窓にぶつかって軽い脳震盪を起してしばらく動けません
-

エゾハルゼミの1㎝ほどの小さな抜け殻
-

地面に埋もれた古いホオノキの実から発生するホソツクシダケ
-

タンナサワフタギの小さな白い花が満開に
-

珍しく手の届く高さで開花したヒコサンヒメシャラの花
清々しい青空を背景に新緑が美しい季節になりました。木洩れ日をとおしてみた風景を眺めていると、身体が緑色に染まっていくような錯覚を覚えます。これはまさに森のマイナスイオンが身体に取り込まれている証拠かもしれません。
葉緑素を持たない寄生植物であるギンリョウソウ(銀竜草)が小さな群落をつくって花を咲かせています。まるで、銀色のタツノオトシゴが群れているように見えます。名前は「銀色の竜のような草」と言うことで、辰年の年男ならぬ、「年草」とも言えます。
日当たりの良い林縁にはヤブウツギが沢山生えていて、この時季深紅の花を沢山咲かせます。惜しむらくは、花の命が短いことです。特に、雨に打たれてしまうととたんに萎れてしまいます。同じスイカズラ科のツクバネウツギは花の根元に羽根衝きの「衝く羽根」が見られることから付いた名前です。
林床に黒っぽい羽根がまとまって沢山落ちています。これはキジバトが捕食者である猛禽類(恐らくは、タカの仲間)に捕えられたのです。捕えられ、その場で羽根をむしられてタカのヒナが待つ巣へと持ち帰った証拠です。
5月になって今年の自然体験教室が始まりました。富士宮市の小学生を中心にたくさんの子どもたちがやって来て、自然の豊かさと大切さ、不思議な一面など五感を使って学んでいく場となっています。
ゴールデンウィークの最終日に野鳥の会南富士支部による鳥獣生息調査が行われました。1年に4回(5月と6月の夏鳥シーズン、1月と2月の冬鳥シーズン)モニタリング調査を委託しており、今年で25年目になります。この時季は樹々の葉が生い茂るので、啼き声は沢山しても、鳥の姿を見かけることは多くないです。しかし、今回の調査では珍しくアオバト、シメ、ミソサザイ、キビタキ、カケスなど割りと多くの鳥を見かけることができました。
-

新緑の森から見える青空はなんとも美しい
-

新緑の中を歩いていると身体が黄緑色に染まりそうです
-

春を代表する草花の1つ、ニリンソウ
-

葉緑素を持たない寄生植物のギンリョウソウ(銀竜草) 辰年の今年にはピッタリな花です
-

ミヤマザクラは一般的なサクラとは少し趣きが違います
-

深紅の花をつけるヤブウツギ たくさんの花をつけるので辺りが赤く染まります
-

森の中に鳥の羽根が散乱して…
-

どうも、キジバトの羽根のようです ここで捕食されたらしい
-

ツクバネウツギの花の付根には名前の由来である羽子板で「衝く羽根」があります
-

春先に咲くオオイヌノフグリによく似たヤマクワガタ
-

日差しを受けて樹の幹に生えているコケが大変美しい
-

大規模な小学校の自然体験教室
-

枝にとまっているアオバト
-

大きな嘴をもつシメは眼つきが鋭く、嘴の色が春~夏は鉛色になる
-

小さな躰のミソサザイが懸命に啼いてます
※野鳥の写真はいずれも「野鳥の会」会員の望月さんのご厚意で提供していただきました