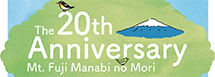自然あふれる富士山2合目の「まなびの森」フォレストアークから
四季折々のようすやボランティア活動についてお伝えします。
みなさん是非「まなびの森」へ足をお運びください。
お待ちしております。
富士山「まなびの森」フォレストアーク副館長・管理人
沢田明宏
2024年がスタートしました。
昨年末以来、小雨であったため、富士山が真っ白に雪化粧した姿をあまり見られませんでしたが、ようやく1月半ば過ぎの寒波で5合目あたりまで雪化粧しました。やはり、冬の富士山は雪化粧なしでは語れません。
冬枯れの「まなびの森」は遠くまで見通せます。晴れた日には、トレールから雪をいただいた富士山も、駿河湾も、伊豆半島も、三保の松原も見えます。冬のトレール歩きのご褒美のようなものです。
森の茂みに日に照らされて白くキラキラしているように見える塊りがあります。近づいてみると、それはボタンヅルの実の塊だと分かります。実に沢山の毛が生えており、それが日光に照らされているのです。
見るものが少ない冬の森で次に目立つのはキハダの黄色です。エサとなる食べ物が少ない冬の森でシカが好んで齧っているのはキハダの根際の樹皮です。樹皮が齧られると黄色い肌を見せるのが名前の由来で、人間にとっては漢方胃腸薬である「黄檗(オウバク)」となります。
1月の終わりに今冬最初の積雪がありました。わずか1~2㎝ですが、その積雪のためいろいろな動物たちの足跡が雪上に残されていました。シカ、テン、タヌキ、ノウサギ、そして野鳥も。
中でもノウサギの足跡は少し変わっています。進行方向の前側が大きく、後ろ側が小さいです。
小さいのが前足で、大きいのが後ろ足です。前足を地面に着いて、身体を縮めて後ろ足を引きつけて前足の更に前に着地させる。そういう跳び方をしているので、後ろ、前という順番になっています。植生回復の植樹で草地が少なくなり、ノウサギを見かけることは減りましたが、こうして積雪があると足跡で存在が分かります。
冬には冬の森の楽しみ方があります。
-

やっと綺麗に5合目あたりまで雪化粧した富士山
-

フォレストアークを出てすぐ、「まなびの森」トレールの入口からの富士山
-

遠目には白い花が咲いているように見えるボタンヅルの種
-

ボタンヅルの実の近影
-

シカによる皮剥ぎがあり鮮やかな黄色が目立つキハダ
-

「海の見えるケヤキ」の向こうに光る駿河湾
-

海の見えるケヤキの背景は駿河湾と伊豆半島
-

薄っすらと雪化粧したフォレストアーク
-

フォレストアーク前に残っていたキジバトの足跡
-

雪の上のノウサギの足跡、右側の2つが前脚、左側が後脚 ウサギは右から左に移動した
真冬の「まなびの森」でとにかく目につくのは地面から立ち上がる大きな霜柱です。時には10㎝を越えて大きくなり、昼間もとけないままとなります。
葉が落ち切った冬枯れの森は見通しが大変良く、東は伊豆半島から駿河湾を挟んで西の美保の松原までが樹々の間から望まれます。写真でご紹介できないのが大変残念です。
樹の上を見上げると、高い場所に丸いボール状の塊となっているヤドリギがあります。ヤドリギは常緑の半寄生植物で落葉広葉樹の枝や幹に根を喰い込ませるようにして生長しています。ヤドリギは自分で光合成していて、ミネラルを含んだ水分を取りついた樹からもらう半寄生と言うことになります。西洋ではヤドリギは古くから神聖視され、森の精が宿ると言うことからクリスマスに家の玄関につるされたりしています。
ほとんどのヤドリギは高い枝にくっついていますが、たまに2~3mほどの高さにあったりします。
「まなびの森」プロジェクト開始25周年と世界文化遺産登録10周年と言う富士山にとって記念すべき2023年もいよいよ終わります。
1年間ご愛読ありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。
-

寒さで10㎝以上と大きく育った霜柱
-

ヤドリギの黄色い実は冬の野鳥の大好物
-

3mほどの高さにあるヤドリギ
-

早朝に飛行機の窓越しに眺めた富士山 左下には箱根の芦ノ湖が見えている
今年は大きな台風がなく、木の葉が風で擦れあうことが少なかったこともあって、紅葉が色鮮やかだったように感じます。そんな11月の初めに一晩強い風が吹いたことで、樹々の葉っぱが一気に吹き落とされました。フォレストアークの黒い屋根に大量の落ち葉が積もり、見た目には茶色い草葺きの屋根と見紛うばかりになりました。こんな風景とは初めて出逢います。
里山などのドングリ類の実りが少ないことがニュースになっていますが、「まなびの森」では今年ケヤキとツルマサキの実りが目立っています。
ケヤキはフォレストアークの周囲にまるで小粒のアラレを撒いたようにたくさん実り、ツルマサキは離れたところからでもハッキリ見えるほどに多くの赤い実をつけています。特に、ツルマサキは冬の野鳥の大好物なので、給餌にたくさんのヤマガラやシジュウカラ、アトリなどの鳥たちが集まってきています。
落ち葉の上に動物の糞を見つけました。大きさと見た目、色の違う2つの糞が重なるように落ちていました。下側の少し太めの糞には毛が交じっていることから恐らくキツネのものでしょう。その上に重なるようにあるものはそれより細く、小指ほどの太さで色も黒くて植物の種がたくさん交じっていることからテンの落とし物でしょう。どうも、身体の小さなテンが、自分より体つきがずっと大きなキツネに対して縄張りを主張しているとしか思えない様子を想像するとなんとも微笑ましいではありませんか。
森は完全に冬枯れとなって見とおしがよくなり、鳥の姿も良く見える冬の到来となりました。
-

西臼塚駐車場の真っ赤に色づいたモミジと富士山
-

林床にくり広げられた「葉っぱの錦」
-

今年はツルマサキの赤い実が豊作です
-

ある日、強風でフォレストアークの周りの樹々が一気に落葉し、屋根が枯れ葉で埋め尽くされました
-

この冬の初霜となります
-

ナナカマドの赤い実が沢山
-

青空に映えるナナカマドの実
-

2種類の糞が重なるようにありました 大きいのがキツネ、小さいのがテンと思われます