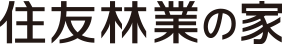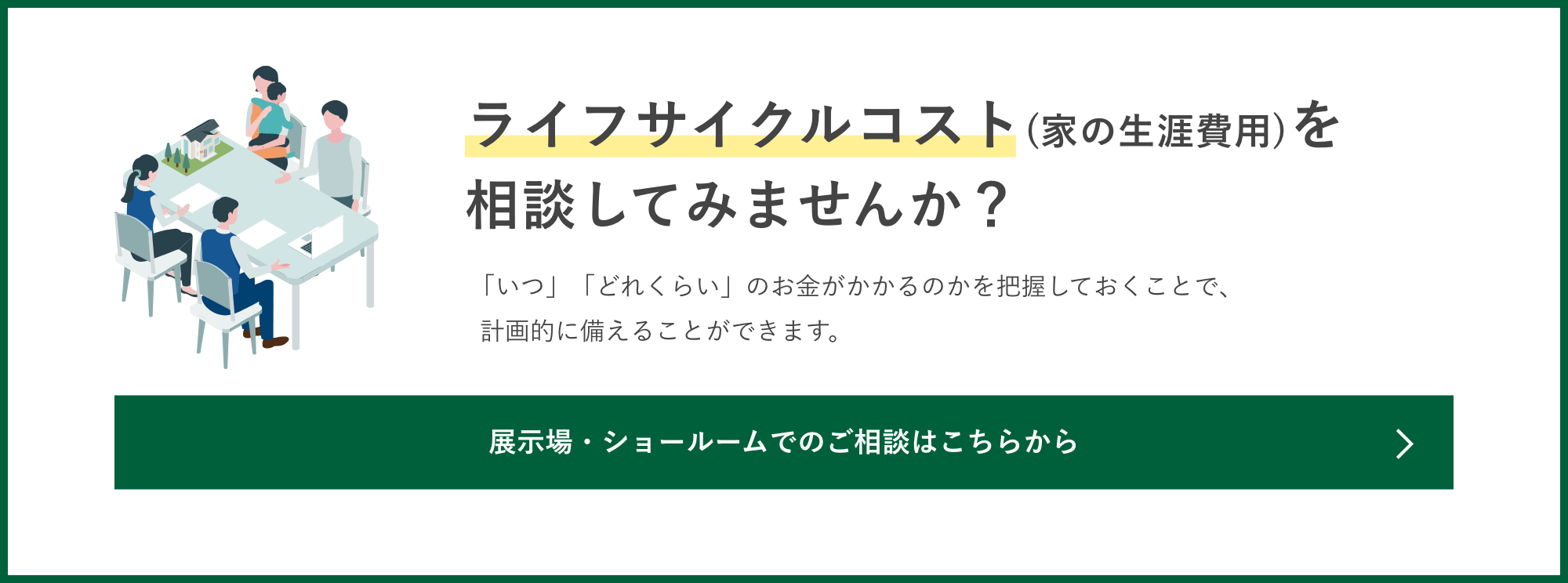資金計画用語集
住まいの資金計画に必要な専門用語を
わかりやすく解説しています。
あ行
- 頭金
- 住宅の購入資金のうち、一時金で支払う部分です。
- 印紙税
- 不動産取引の際に作成する売買契約書、請負契約書、また購入資金の仕入れに伴って作成される金銭消費貸借契約書に課税される国税です。
か行
- 火災保険
- 建物や家財などの火災やその他の災害などによる損害を補償する保険です。
- 借入金利
- 借入金額に対して支払う利息の割合です。
- 元金均等返済
- 借入金額を返済回数で割った金額を毎回返済額の元金部分とし、毎回の借入金残高に対する利息分を上乗せして返済する方法。借入初期の返済額は多くなりますが、返済が進むにつれ返済額が減少していきます。また、利息部分の負担が「元利均等返済」と比べて少なく同じ設定のローンであれば、総返済額は少なくなります。
- 元利均等返済
- 毎回返済額(元金と利息の合計)が一定で、徐々に元金部分が増えていき、利息部分が減っていくのが元利均等返済の特徴。返済額が一定なので、返済計画が立てやすく一般に多く利用される方法です。
- 繰上げ返済
- 一定額以上のまとまった資金を返済の途中で元金部分に繰り入れる方法。本来返済予定だった期間の元金の一部を一括で返済するので、将来的には利息部分の返済を減らすことができます。返済方法としては、期間短縮型と返済額軽減型があります。
- 期間短縮型は、毎回の返済額は変えずに、返済期間を短くする方法。
- 返済額軽減型は、返済期間は変えずに、毎回の返済額を少なくする方法。
- 固定金利型
- 当初確定した金利が返済期間中、金利が変動しないタイプ。返済額が変動しないので、生活設計に合った返済計画を立てるのに適しています。
- 固定金利選択型
- 固定金利選択型は、変動金利をベースに3年、5年などの一定期間、適用金利を固定するタイプ。固定金利期間は契約時に決めますが、返済開始後は固定期間が満了した時点で、次の期間も金利を固定するか否かを選択します。金利の固定を選択しない場合、以降は変動金利になりますが、いつでも固定金利選択型に戻すことができるタイプが一般的です。
- 固定資産税
- 毎年1月1日現在で土地・建物・償却資産を所有している人に対してかかる地方税。税額は固定資産税評価額に1.4%をかけた額です。
さ行
- 自己資金
- 手元にある現金のこと。住宅を購入する際、一時金で支払う頭金と諸費用を自己資金から支払うのが一般的です。
- 地震保険
- 地震による災害で発生した損失を補償する保険です。
- 事務手数料
- 住宅ローンを借り入れる際にかかる手数料です。
- 収入合算
- 本人の年収のみでは希望額の借入れが難しい場合に、安定収入のある配偶者などの家族1名の収入を加えることで、希望額の融資を受けられる場合があり、これを収入合算といいます。
- 収入基準
- 年収に対する返済額が何割まで借り入れできるかという基準です。
- 住宅ローン控除
- 住宅ローンを用いて住宅を購入した場合、一定の条件を満たせば、収めた税金から控除される制度です。
- 諸費用
- 住宅を購入する際、物件の購入金額以外にかかる各種税金や手数料です。
- 総返済額
- 返済期間内に支払う元金と利息を合計した額です。
た行
- 団体信用生命保険
- 住宅ローンの借主が死亡したり重度の後遺障害を受けた場合に、ローンの残債が一括返済される保険制度です。この保険に加入していれば、残された家族には以降のローン負担が残りません。
- 仲介手数料
- 仲介会社を通して不動産の取引をしたときに、業者に支払う手数料です。
- 都市計画税
- 都市計画法で指定された市街化区域内の不動産に課税される地方税。税額は固定資産税評価額に市町村が定める税率をかけた額です。
な行
は行
- 付帯工事費
- 建物以外にかかる工事費です。
- 不動産登記
- 土地及び建物の物理的現況と権利関係を公示するために作られた登記簿に登記することです。
- 返済期間
- 住宅ローンの借入金と利息を返済するための期間です。
- 返済方法
- 住宅ローンの返済方法には「元利均等返済」と「 元金均等返済」の2種類があります。
- 変動金利型
- 市場金利に連動して年2回金利が見直されるタイプ。返済開始後にベースとなる市中金利が上がると住宅ローンの金利も上昇します。変動金利の返済額は、5年ごとに見直されますが、金利見直し後の返済額は見直し前の25%以上にはならないというルールがあります。
- 保証料
- 住宅ローンの返済中に、何らかの事情で返済が困難になった場合、信用保証会社に返済を肩代わりしてもらうために、ローンの借入時に金融機関に支払う費用です。
- ボーナス併用払い
- ボーナス月(年2回)に、毎回の返済額に一定額を上乗せして住宅ローンを返済する方法です。
ま行
- 毎月返済額
- 住宅ローンの返済のために、毎月支払う額です。
や行
ら行
- 利息
- 借入した場合、賃貸料として借りた人が貸した人に支払う額です。