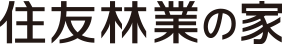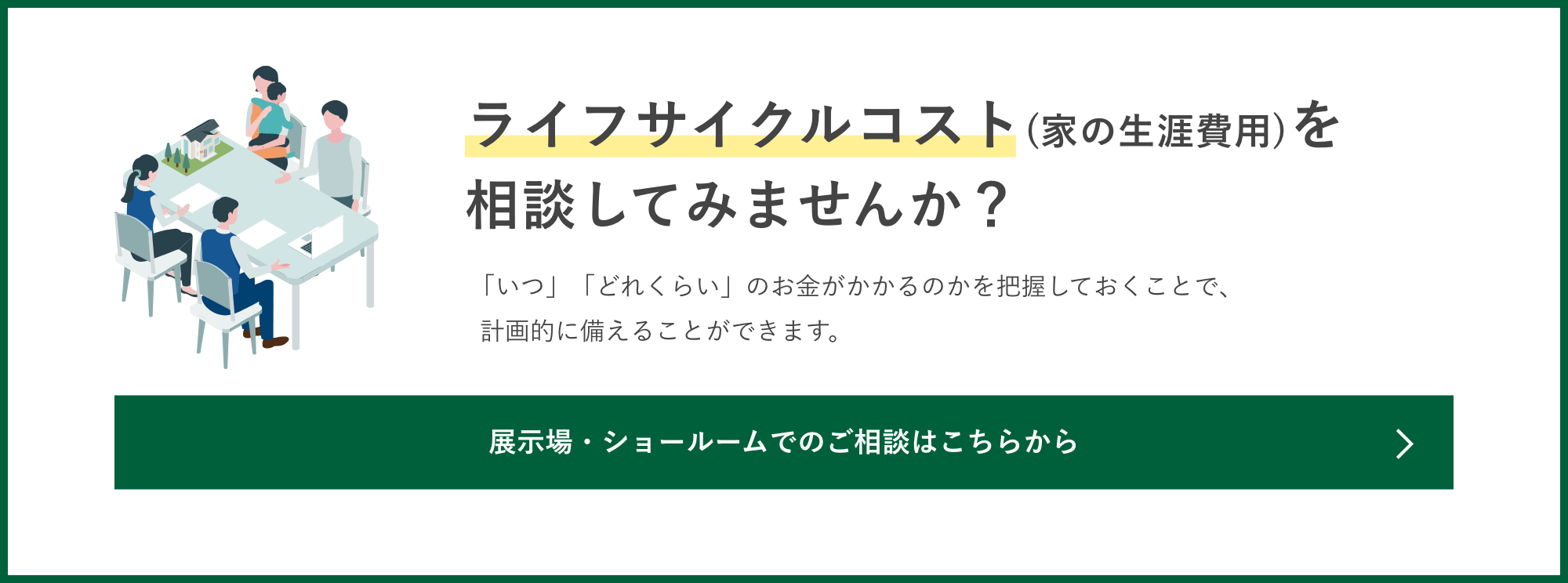マイホームの取得を計画しているご家庭で夫婦それぞれに収入がある場合の住宅ローンを借入する方法には「連帯債務」と「ペアローン」という2つの方法があります。
また、住宅ローンを利用する場合は、所定の要件を満たせば、国の「住宅ローン減税制度」を利用することができます。
今回のコラムでは、住宅ローンを利用するケースで、「連帯債務」を選択した場合にポイントとなるところを確認していきます。
住宅ローンを「連帯債務」にする場合の
住宅の持ち分と「住宅ローン減税」
公開日:2025.05.19
- 住宅ローン減税

「連帯債務」とは
「連帯債務」とは、取得する住宅を共有名義にして、共同責任で住宅ローンを返済する住宅ローンの申込みをする方法で、夫婦の場合は、一方を主債務者、もう一方を連帯債務者にする方法です。
住宅ローンを借入する人の名義は主債務者となり、金融機関への住宅ローンの返済の全額を主債務者が行います。
「連帯債務」を夫婦で利用する場合は、夫婦の一方が連帯債務者になることで、夫婦間で取り決めした割合に応じた部分の住宅ローンの返済額を家庭内(夫婦間)で負担することになります。
この夫婦間での負担割合は相互の収入の割合などを目安にして、自由に決めることができます。
ただし、取得する住宅の夫婦間の登記上の持ち分は、この取決め割合と同じにするのが原則です。
住宅ローンを借入する人の名義は主債務者となり、金融機関への住宅ローンの返済の全額を主債務者が行います。
「連帯債務」を夫婦で利用する場合は、夫婦の一方が連帯債務者になることで、夫婦間で取り決めした割合に応じた部分の住宅ローンの返済額を家庭内(夫婦間)で負担することになります。
この夫婦間での負担割合は相互の収入の割合などを目安にして、自由に決めることができます。
ただし、取得する住宅の夫婦間の登記上の持ち分は、この取決め割合と同じにするのが原則です。
連帯債務の場合は夫婦それぞれが住宅ローン減税を申請することができます
「住宅ローン減税制度」は、住宅ローンを借入している人が使える所得税(場合によっては住民税)からの減税制度です。
新築住宅の場合は、返済開始から13年間は年末の借入金残高の0.7%(控除対象となる借入金の限度額は、取得した住宅の環境性能等に応じて定められた金額)を、「確定申告」もしくは「年末調整」で確定した所得税額から控除することができます。
(2025年5月時点)
所得税から控除しきれない金額は、所定の金額までを翌年の住民税から(最大97,500円)控除されます。
新築住宅の場合は、返済開始から13年間は年末の借入金残高の0.7%(控除対象となる借入金の限度額は、取得した住宅の環境性能等に応じて定められた金額)を、「確定申告」もしくは「年末調整」で確定した所得税額から控除することができます。
(2025年5月時点)
所得税から控除しきれない金額は、所定の金額までを翌年の住民税から(最大97,500円)控除されます。
住宅ローン減税を受けられるのは住宅ローンの債務者になっている人
「連帯債務」の場合は、主債務者も連帯債務者も住宅ローンの債務者なので、それぞれ住宅ローン減税を申請することができます。
「連帯債務」の夫婦それぞれが住宅ローン減税で使える年末の借入残高は、住宅ローンの残高全体のうち夫婦間で決めた住宅ローンの負担割合に応じて決まります。
例えば、夫の負担割合が60%で妻の負担割合が40%の場合、住宅ローンの年末残高が4,000万円とすると、夫が住宅ローン減税の申請で使える年末残高は2,400万円、妻は1,600万円です。
「連帯債務」の夫婦それぞれが住宅ローン減税で使える年末の借入残高は、住宅ローンの残高全体のうち夫婦間で決めた住宅ローンの負担割合に応じて決まります。
例えば、夫の負担割合が60%で妻の負担割合が40%の場合、住宅ローンの年末残高が4,000万円とすると、夫が住宅ローン減税の申請で使える年末残高は2,400万円、妻は1,600万円です。
「連帯債務」で「住宅ローン減税制度」を利用する場合の確定申告と年末調整
住宅を取得した人は、翌年の確定申告で「住宅ローン減税制度」を利用する申告手続きをしなければなりません。
給与所得者は、最初に確定申告をすると、翌年からは年末調整の対象になります。
年末調整では、主債務者、連帯債務者の両方が、住宅ローンの負担割合に応じた住宅ローン残高で「住宅ローン減税」の申請をすることができます。
給与所得者は、最初に確定申告をすると、翌年からは年末調整の対象になります。
年末調整では、主債務者、連帯債務者の両方が、住宅ローンの負担割合に応じた住宅ローン残高で「住宅ローン減税」の申請をすることができます。
夫婦間での負担割合と住宅を登記する際の持ち分には注意が必要
住宅ローン減税の対象となる夫婦間での債務の負担割合は、取得した住宅を登記する際の持分割合と同じにします。
例えば、物件価格が5,000万円、このうち頭金の1,000万円を夫が負担した場合、住宅ローンの借入金額は4,000万円です。
仮に「連帯債務」で夫婦間の負担割合を夫と妻で50%ずつにした場合は、それぞれが住宅ローンを返済するために負担した金額は2,000万円です。
ただし、夫は頭金1,000万円を出しているので、住宅を購入する為の負担割合は、夫が3,000万円、妻は頭金を負担していないので、2,000万円です。
住宅の登記の持ち分はこの割合と同じにするのが原則です。
上記のケースでは夫が60%(5,000万円のうち3,000万円)、妻が40%(5,000万円のうち2,000万円)です。
夫婦各々の住宅ローンの年末残高は、この持ち分と同じ割合で申請します。
この例で、住宅ローンの年末残高が3,000万円の場合は、夫は3,000万円うち60%の1,800万円、妻は同じく40%の1,200万円です。
住宅の持ち分を夫が50%、妻が50%の共有とすると、夫から妻へ10%分を贈与したことになるので贈与税の課税対象になります。
「連帯債務」の場合の住宅ローン減税に使う債務の負担割合は、取得した住宅の登記の割合が大きなポイントになってきます。
住宅の共有持分については、住宅の登記を行う前に、税務署などにご相談しましょう。
例えば、物件価格が5,000万円、このうち頭金の1,000万円を夫が負担した場合、住宅ローンの借入金額は4,000万円です。
仮に「連帯債務」で夫婦間の負担割合を夫と妻で50%ずつにした場合は、それぞれが住宅ローンを返済するために負担した金額は2,000万円です。
ただし、夫は頭金1,000万円を出しているので、住宅を購入する為の負担割合は、夫が3,000万円、妻は頭金を負担していないので、2,000万円です。
住宅の登記の持ち分はこの割合と同じにするのが原則です。
上記のケースでは夫が60%(5,000万円のうち3,000万円)、妻が40%(5,000万円のうち2,000万円)です。
夫婦各々の住宅ローンの年末残高は、この持ち分と同じ割合で申請します。
この例で、住宅ローンの年末残高が3,000万円の場合は、夫は3,000万円うち60%の1,800万円、妻は同じく40%の1,200万円です。
住宅の持ち分を夫が50%、妻が50%の共有とすると、夫から妻へ10%分を贈与したことになるので贈与税の課税対象になります。
「連帯債務」の場合の住宅ローン減税に使う債務の負担割合は、取得した住宅の登記の割合が大きなポイントになってきます。
住宅の共有持分については、住宅の登記を行う前に、税務署などにご相談しましょう。
まとめ
「連帯債務」を夫婦で使う場合は、それぞれが住宅ローン減税を申請できますが、住宅ローン契約の当初は配偶者(一般的には連帯債務者)に所得があっても、その後に産休や育休あるいは、専業主婦になることなどで所得がなくなることで、住宅ローン減税の適用が受けられなくなる場合もあります。
住宅ローンは長い期間に渡って返済が続く大きなお金の借入です。
家族のライフプランや家計の資金計画の青写真をしっかりと考えたうえで、将来の家計運営にとって安全で安心できるものを検討しましょう。
住宅ローンは長い期間に渡って返済が続く大きなお金の借入です。
家族のライフプランや家計の資金計画の青写真をしっかりと考えたうえで、将来の家計運営にとって安全で安心できるものを検討しましょう。